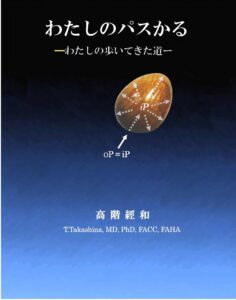ジェックスの設立者で理事長の髙階經和先生が、お生まれになった1929年から現在進行中の研究成果まで、90年を超える人生と研究をみずからまとめておられます。
内容はもちろん、読み物としても大変興味深い「自叙伝」となっています。ぜひお楽しみください!
*****************************************************
『わたしのパスかる!』(連載第18回)
ーわたしの歩いてきた道ー
ジェックス理事長 髙階 經和
第4章:-1995年~2022年-
6.再びニューオーリンズヘ
1998年春、ニューオーリンズ市。関西国際空港を出発してから18時間後に、わたしたちは、ニューオーリンズのモアゾン空港に降り立った。午後9時、アメリカ南部特有の、ムッとするような、湿った重い空気が空港構内に漂う。空港からタクシーに乗ったが、黒人のドライバーが話しかけてきた。実にはっきりした英語なので少々驚いた。わたしたちが40年前に住んでいたと話したところ、ドライバーは急に親しみを覚えたのか
「あなたはドクターですか?」
「ええ、そう。でもどうして分かったの?」
「昨日あたりから、急に、外国人のお客さんが増えましてね。皆さんドクターなのですよ」
「なるほど」
それから彼は、最近は治安が良くなったことや、わたしが勤務していたニューオーリンズ慈善病院も内装が新しくなって見違えるように美しくなったこと、などを誇らしげに話してくれた。
翌朝の3月7日、8時にホテルのロビーで朝食を取ったが、外に出てみると、珍しく天気は曇りで風が強く大変寒い朝である。ホテルからコンベンション・センターまで、歩いて僅か10分の距離だったが、夏服を着ていたわたしは思わず身震いがした。
このコンベンション・センターは、今までアメリカ各地で見てきたものなかで、最大規模ではないだろうか。入り口から広大な展示場が一キロは続き、有名な「ニューオーリンズ・ブリッジ」の手前で終わっている。ミシシッピー河に沿って、8年前に完成したショッピング・モール「リバー・ウオーク」も幾分古びて見える。
正午に、コンベンション・センターの「京都科学」の展示コーナーに行ってみると、「イチロー君」が再び人気者になっていた。
「この値段は、アメリカドルでどれ位か?」
「アメリカのハーヴェイと、どう違うのか?」
「ヨーロッパに、代理店があるか?」
などなど、昨年、アナハイムでの展示の時もそうだったが、世界中から集まった多くのドクターが、ブースを訪れていた。
何よりも驚いたのは、マイアミ大学医学部でゴードン教授と一緒にハーヴェイの制作を担当している、技術主任のデビット・ローソン ( David Lawson )が、ゴードン教授の依頼で展示コーナーを訪れたことである。彼は仔細に「イチロー君」を観察していたが、わたしに向かって言った。
「このシミュレータは、確かにハーヴェイ君より遥かに良く出来ている。素晴らしいものだ」
わたしが清水、片山の両氏の協力によって完成した「イチロー君」が確かに、ハーヴェイとは全く違った方法で作られたものかどうかを、彼は自分の目で確かめたかったに違いない。その瞬間、わたしは遂に「イチロー君」が「ハーヴェイ」を越えたと確信した。
3月7日の夕方、わたしたちの41年来の友人、有村章先生(チュレーン大学医学部内科教授で、神経内分泌学の世界的権威)夫妻と、前出のアリゾナ大学医学部のエーヴィ教授夫妻と共に、この街で有名なレストラン、「コマンダーズ・パレス」の2階に食事の予約を取った。まず一階のカウンターで気付いたことであったが、入り口が非常に狭く、それに階段が狭く、建物は木造で古い。2階に上がってからも、小さな小部屋をいくつも通り過ぎていった。そして、その途中にも下に降りる階段が二つもあった。不思議に思っていたが、お互いに久し振りの挨拶を済ませて席に座った。
「髙階さん、このレストランは昔、娼婦宿だったのですよ」
と有村先生がいったので、やっと謎が解けた。突然、このレストランが百年前の姿にタイムスリップした様に感じた。これがわたし達の8年ぶりに交わした最初の話題である。
わたしたちがこの街に住んでいた頃、アメリカ人の友人が、よく「ニューオーリンズへ旅行した」と言うと、「決していつ行ったとか、何をしたかとか、聞いてはいけないというのが我々の間では常識なのだ」と言った台詞を思い出した。どうやらニューオーリンズは、往年の旅行者にとっては、エキゾティックな魅力に富んだ街ではあったが、と同時に彼らが自らの行状については語るに語れぬタブーの街だったらしい。ディナーの前にエーヴィ教授から
「ケイ、来年のアメリカ心臓病学会の直前に、わたしの大学で『シミュレータ“K”』を使って聴診の講義をしてくれないか?」との申し出があった。
「直前だったら何時がいいかな?」
「3日くらい前に来てくれたら、ちょうど此方も都合がいいのだが」
「OK」といって、わたしはドクター・エーヴィの大学での講義を引き受けた。
エーヴィ教授夫妻もすっかりわたしたちの会話にとけ込み、気がつくと時計は午後11時を廻っていた。エーヴィ先生も上機嫌だった。有村先生に「髙階さん、明日、夕方に自宅にお出で下さい」と誘いを受けた。翌日もわたしは一日中、「イチロー君」のデモンストレーションや、説明に追われて忙しい時間を過ごし、午後5時にホテルに帰った。
夕方7時に有村先生の車でミシシッピー河を渡り、オーロラ地区という古いプランテーション・ハウス(建築後200年という、南北戦争当時の、豪農の館である)の広大な先生の自宅を訪ねた。日本では想像も付かない一面の芝生に囲まれた広い庭、そして平屋の館。あの『風と共に去りぬ』の場面に登場するような開拓時代の建物まさにアメリカ南部の歴史の証人がそこにあった。
有村先生ご自慢の「クローフィッシュ」(つまり日本では「ザリガニ」)を、大皿一杯に目の前に置かれて、思わず
「どうして食べるのですか?」とわたし。
「まず頭の部分をちぎって、小指で脳味噌を掻きだして、最初に食べるのです」と有村先生。
「・・・・」
「それから胴体の方を割って、尻尾の方を引っ張れば身が出てきます」と、実演して見せてくれた。
有村先生の言われた通りに食べてみたが、なかなかの味である。
「ところで、わたし達が来た直後の『新春の船火事』のときは大変でしたね」
「ああ、覚えていますよ。わたしたちがニューオーリンズに来て、最初の1959年の正月でしたからね」
「寒いミシシッピーの川面を見詰めて、行方不明になったシップ・ドクターを探したが、結局、見つからなかったのですね」
「それより、わたしの患者さんのお一人で、そのシップ・ドクターを知っている方があるのです」
「えっ?」
「実は、当時、その方は当時、船舶会社に勤務しておられました。偶々、挨拶に来られた丸顔の若いドクターがおられたことを覚えていた、と言われるのです。わたしが、以前に書いたエッセイをお読みになって、すぐに(あの時のドクターだ)と直感されたようです」
「分からないものですね、40年の月日が経ってから、そのドクターを知っていた方が、おられたとは」
「本当に、人生って色んなことがあって不思議ですね」
2人は、その夜様々な思い出に華を咲かせたのだった。
(*しかし、世界的な学者として神経内分泌伝達ホルモンを研究し、ノーベル賞の候補に何度も挙がった有村章先生も、2009年、多発性骨髄腫のために亡くなった。わたし達夫婦と共に4年の間、ニューオーリンズで過ごした親友の冥福を心から祈りたい。)
7.ジェックス研修センター開設
1999年秋、大阪、10月1日、わたしが主宰している社団法人臨床心臓病学教育研究会(JECCS)は、新大阪駅のすぐ近くの太平エンジニアリング・ビルの九階フロアを借り、「ジェックス研修センター」をオープンした。これはわたしが、17年近くも前から提唱していた日本版「ハート・ハウス」設置への、第一歩だったのである。このセンターでは、毎月、医師、医療関係者に対する研修会が、開催されていたが、11月と12月5日(土)回に亘って、大阪吹田市にある国立循環器病センターに各国からJICAのプログラムで留学しているドクターを対象に、「心臓病患者シミュレータを使った研修を行って欲しい」との依頼があった。
わたしは、この事を社団法人の理事会にかけて賛成を得た。事前に元大阪市長の大島靖氏とJICA大阪研修所の田上所長が、研修センターに視察に来られた。お二方には「イチロー君」の臨床医学教育における必要性について説明し、実際に「イチロー君」を起動させて説明したが、教育機器としての素晴らしさが十分に伝わった結果、今回の研修となったのである。五名の留学生医師達は、それぞれ国も異なり、医学教育の背景も異なっていたが、彼等に共通していたことはベッドサイドにおける診察法の基本を身につけていたことだ。彼らは「イチロー君」を見るなり驚きの声を挙げた。
「これは凄い。こんなシミュレータは見たことが無い!」
頸静脈波の診かたに関しては、さすがに慣れていなかったようだが、全身動脈拍動の触診の手技、そして心尖拍動(心臓の尖端部が一心拍毎に、胸壁を押し上げる動きで、各心疾患によって、独特の動きが出る)の触診も充分に慣れていた。そしてわたしが更に驚かされたのは彼等の聴診における技術の高さである。最初の一時間、オリエンテーションをおこなった。その後、各自に各心疾患について鑑別診断をしてもらったが、5名とも聴診だけでピタリと見事に診断をつけた。
いままでわたしは、数え切れない程のベッドサイド教育を医師や、医学生、看護師などに行なってきたが、彼等ほど短時間に「イチロー君」の身体所見を正確に把握し、研修の成果を上げたグループは他にはない。ある医師は「自分の国には、心エコーの器機もないし、頼れるものは自分の診察技術と心電図だけだ」と話していたが、わたしは全員の医師に向って、
「皆さんは、わたしが研修をして来たドクターの中で、最高のグループと思います。この研修を機会にそれぞれの国に帰っても、わたしの教育の仕方を参考にして、若いドクターや医学生達を教えてほしいと思います」
と話した。わたしが今まで臨床心臓病学を教えてきた事について
「わたしは40年まえにアメリカに留学し様々なことを学びました。当時の若い自分にとつては強烈なインパクトでした。そのインパクトに支えられ、わたしは臨床心臓病医としての道を歩いて来たわけです。現在、今度はわたしが経験し身につけた知識を皆さんに還元する番です。一つでも正確な知識を後輩に伝えること、それが教育です。そして“どう教えるか”と言う事を絶えず念頭におき、“どう教えてはいけないか”を知ることです」と話した。
彼等は深く領き、
「プロフェッサーの講義は素晴らしく、今迄に自分の国で一度も聞いたことのない程、魅力的なものでした。「イチロー君」も本当に凄い教育効果がありました。できれば、ぜひ購入したい位です。どうも有難うございました」
と言って、彼らは1人ずつ握手を交して、ジェックス研修センターを後にした。その日の研修は終ったのだが、5名の強い要請があり、2回目は平成11年11月18日に、心電図と身体所見との関連について話した。彼等が再び満足したことは言うまでもない。やがて今回の留学生達は12月3日に、はじめて経験した「イチロー君」の教育的魅力を満喫し、惜しみながら母国へと帰って行った。
今回の2回の研修を通して得たものは、外国人の医師達の一人一人が臨床の基礎知識と手技を身につけていたということである。今日のように「ハイテク依存症」に罹っている日本の若い医師達には耳の痛い話だが、これは現実である。「臨床の基本は、あくまでも患者の話に耳を傾け、身体所見を診るためには自らの五感を使い、探偵のような鋭い観察眼と同時に人間的な優しい心で接することである。それが既に一世紀まえにジョーンズ・ホプキンス大学の内科学の世界的確威だったオスラー卿(Sir William Osler)が、若い後輩の医師達にいつも、患者のベッドサイドで「臨床医学とは科学とアート(Science and Art)である」と、説いていた理念でもある。
わたしの友人でチャイナ・メディカル・ボード(China Medical Board)の国際医学教育委員長のアンジェイ・ボイチャック博士(Dr. Andrzej Wojtczakは現在、米国国際医学教育研究所所長で、前世界保健機関WHO神戸センター所長)が指摘しているように、日本の医学部卒業生の国際的レベルは、世界で戦後50年以上も経った現在も、依然としてその臨床技術レベルが20位以内になれないでいるのが現状である。研究分野で世界をリードしているのとは正反対である。
その理由は、語学力の不足もさることながら、臨床の現場に役立つ知識と、ベッドサイド手技を教える能力のある指導医が少ないことに他ならない。わたしはこれから日本の臨床医学教育が本当に国際的に通用できる臨床医を育てなければならないことを、改めて考えさせられた次第である。
【・・・次回に続く】
※「わたしのパスかる」へのご感想をぜひお寄せください。 office@jeccs.org