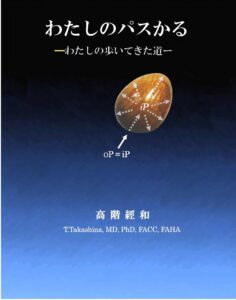ジェックスの設立者で理事長の髙階經和先生が、お生まれになった1929年から現在進行中の研究成果まで、90年を超える人生と研究をみずからまとめておられます。
内容はもちろん、読み物としても大変興味深い「自叙伝」となっています。ぜひお楽しみください! (連載内容の目次はこちら)
*****************************************************
『わたしのパスかる!』(連載第8回)
ーわたしの歩いてきた道ー
ジェックス理事長 髙階 經和
第二章:-1954年~1971年-
15.大阪に心臓病クリニックを開設
1969年4月、わたしは淀川キリスト教病院から2キロのところにある現在の場所に、循環器科の専門クリニックを開設したが、同時に金子先生の後を継いで神戸大学医学部の非常勤講師となり、二足の草鞋を履くことになった。そして友人でもあり、先輩でもあった第一内科の依藤進助教授(故人)と共著で、イラストを駆使した心臓病学の入門書『心臓病へのアプローチ』を医学出版社の医学書院から出版した。
この本は左右見開きページにイラストと問題形式で作られたもので、従来の教科書には見られなかったユニークな構成の心臓病学入門書として医学生や、若手の医師たちに受け入れられ、現在まで改訂四版を重ねた。また1962年に医歯薬出版社から「クリニカル・プラクティス・イン・カーディオ」を出版しベストセラーになった。更に2009年に新しいスタイルの変えた啓発書として若い医学生や、ドクターのために『心臓病患者の診かた、聴きかた、話しかた』を医学書院から出版した。そしてこれらの著書を出版したことによって心臓病の理解を容易にすることが出来たと考えている。
16.神戸大学医学部でのレクチャー開始(55)
神戸大学医学部で最初の講義が始まった。わたしはチュレーン大学の学生達が行ったケース・ワークアップ(患者さんから病歴を取り、診察のあと鑑別診断を行い、最後に治療方針を立てていく一連のプロセス)を、チョークで広い黒板の端から端まで一杯に一気に書いた後、前列に座っている学生に向かって
“What is your diagnosis? ”(貴方の診断は何かね?)
と英語で聞いた。聞かれた学生は一瞬ポカンと口を開けたままだ。
「諸君、これがアメリカの大学医学部の学生が書くケース・ワークアップだ。これからは君達もアメリカの学生の様に英語で、臨床医学を勉強して行こうじゃないか」
七年前に「淀キリ」のドクター達が経験したように、初めて講義に出席した学生達は一様にカルチャー・ショックを受けた。やがてアメリカの臨床訓練の厳しさと、マン・ツウ・マンの教育でわたしから何かを貪欲に学ぼうと思った何人かの学生達が現われた。
彼らは朝7時から講師室へ集まり、午前8時30分に始まる大学の講義を前に、毎週火曜日には自主的にわたしとの臨床英会話を通して、最新の医学トピックスばかりではなく、臨床医にとって人間的なアプローチが如何に大切かを学んでいった。わたしが指導した彼らは独自の道を歩んで行ったが、中でも傑出した人物として東京慈恵会大学医学部・脳神経外科の大井静雄元教授や、ノーベル賞受賞者となった京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥教授らは最も優れた後輩である。その他の後輩達も次々にアメリカや、ドイツに留学していったが、その後、各大学で教鞭をとり、教育、臨床、研究の面でも国際的な活躍をしている。
日本でもやろうと思えば決して出来なくはない事をしないのは、強固な意志が無いか全くやる気が無いかの、どちらかだ。今日でも積極性に欠ける平均的な人々の意識構造は戦前からまるで変わっていないのではないだろうか。わたしは従来の医学教育には飽き足らず、絶えず新しい臨床心臓病学の教育法を考えていた。
当時、わたしは学生達を教えていて、どうも理解できないことが一つあった。それは他でもない。医学生達は熱心に勉強するが、いざ実際の患者を前に病歴をとり、診察を行うという、基本的な手技を修得する段なると、極めて消極的になり余り関心を示そうとしなかった。その理由はすぐに分った。日米の大学医学部での臨床医学教育システムに、大きな開きがあったからである。州によって異なるが、多くのアメリカの大学では、医学部1年生(3年次)になった時から、患者さんのいる家庭を訪問し、その家族構成や暮らし方や患者さんに対して家族がどう接しているかなどに付いて詳しく調べ、その結果を指導医に報告する。
臨床医学には全くの素人に過ぎない3年次の学生も、次第に臨床医としての仕事や社会的責任の重さを知り、2年の基礎医学教育を終え、5年次から始まる病院での臨床実習や病院での当直などを経験して、6年次やレジデントと共にこなす頃には、彼らも教科書を熟読し、連日行われているレジデントや、指導医達とのディスカッションにより医学知識も徐々に増え、卒業前にはケース・ワークアップも完璧なものとなり、立派な一人前のドクターとして、恥ずかしくない程に成長していくのだ。
それに引きかえ日本の殆どの大学医学部では、こういったシステムは全く無かった。教授や助教授、講師などによる座学形式の講義が大半を占める。講師の中には、自分が学会に発表した研究論文の内容などを得意げに話す人がいる。学生のためのベッドサイドでの講義は、臨床医を育てるために最も大切である臨床知識とマナーと手技を教えることではないか。そうでなければ臨床講義とはいえない。3年次の後半には、当時「ポリクリ」と呼んでいた臨床実習(ドイツ語の「ポリクリニーク」を略した言葉)が始まる。
その「ポリクリ」なのだが、病院の外来では患者さんの数も多く、まして数名の学生が教授の後について診察している後姿を、教授の肩越しに眺めているに過ぎない光景は、まことに奇妙で「果たしてこれが臨床実習なのか?」と感じた。その光景は、わたしが卒業してからも変わっていなかった。2004年以来、卒後研修プログラムが発足し、卒後教育内容もかなり変わってきてはいる。淀川キリスト教病院でわたしと白木が立ち上げた独自の教育法「わたしのパスかる」の一つが漸く認められたのを実感したのもその年であった。日本の臨床医学教育の姿を喩えてみると、体が大きくなっても古い貝殻を尻につけて歩いているヤドカリに似ている。アメリカ流の新しい教育方法が良いと分かってっていても、新しいシステムを取り入れるのが極めて遅い。残念ながらこの傾向は医学のみならずあらゆる分野に見られる。
第二次世界大戦が終わるまで、日本の医学教育制度はドイツ流の医学教育制度を踏襲していたため、殆どの教授達は権威主義的であり、教授を交えて若手の医師たちが自由に自分の意見を述べ、ディスカッションすることを許すような雰囲気はなかった。もし教授に向って、反対の意見でも差し挟もうものなら、そのドクターには将来、昇進の道がないことを意味していたのである。また、学生のためベッドサイド教育の必要性を強調する人達は、皆無に等しかった。本来、大学医学部とは臨床に役立つ医師を育てる医育機関であるべきだ。が、どうだろう。
現実には教授たちにとって、一番大切なことは研究であり、二番目に臨床、そして三番目に教育と言う考え方が、各大学に浸透していたのである。中には教育熱心な同僚に対して
「君は、研究もしないで教育だけでは、偉くならないよ」
という者もいた。大学医学部とは医育機関である以上、臨床医を育てなければならない使命がある。しかし、本末転倒も甚だしいのだが、当時の大学の指導医たちにとって、これが現実の姿だった。
アメリカの大学教授達が、ベッドサイドで患者さんを診察しながら、若い医師たちに診断のプロセスや、その疾患に関する最近の論文の名前や文献を紹介して、鮮やかに鑑別診断を行っていくような光景は日本では決して見られなかった。学生を指導するための指導医を育てることなどは念頭にも無かったのである。従って名目上、指導医と称する先輩の医師たちがいるにはいたが、彼らが学生のためにベッドサイド教育を行なうノウハウを身に付けていなかったことは、残念ながら明らかであった。2004年より、医師国家試験にも臨床診断手技の評価を行なう試験OSCE(objectively structured clinical examination)が行なわれることになり、漸く全国の大学医学部でも臨床に即した研修が行われるようになってきことは喜ばしい傾向である。
【・・・次回に続く】
※「わたしのパスかる」へのご感想をぜひお寄せください。 office@jeccs.org