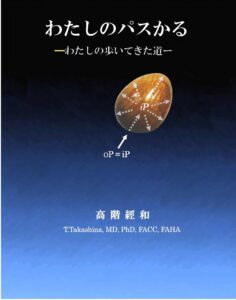ジェックスの設立者で理事長の髙階經和先生が、お生まれになった1929年から現在進行中の研究成果まで、90年を超える人生と研究をみずからまとめておられます。
内容はもちろん、読み物としても大変興味深い「自叙伝」となっています。ぜひお楽しみください! (連載内容の目次はこちら)
*****************************************************
『わたしのパスかる!』(連載第6回)
ーわたしの歩いてきた道ー
ジェックス理事長 髙階 經和
第二章:-1954年~1971年-
12.バーチ教授と再会
1964年5月、京都でアジア太平洋心臓病学会が開催された。わたしはこの学会にチュレーン大学の恩師バーチ教授が、招待演者として出席する予定であることを彼からの手紙で知っていた。学会が開催される二週間前、神戸大学医学部医学英語講座助教授の金子敏輔先生から連絡があった。
「髙階先生、京都で開催されるアジア太平洋心臓病学会でわたしは通訳を頼まれているのだが、貴方に手伝ってもらいたくてね。貴方は専門が心臓病だし、わたしよりも適任だと思うのだが。是非お願いしたい。学会本部の方からも連絡があると思うのだが」
「そうですか、それではお引き受けしましょう」
「どうも有り難う、助かったよ。貴方にオーケーをもらって」
電話の向こうで金子先生のホッとしたような声が聞こえた。
そして学会の始まる前日、わたしはバーチ教授を訪ねて都ホテルの一階ロビーに入っていった。ロビーの椅子に座っていたバーチ教授が目敏くわたしと家内を見つけて張りのある声で「ドクター・タカシナ」と向こうからわたし達に声を掛けてきた。
「ソー ナイス トゥ シー ユウ、ドクター・バーチ」
満面を笑顔に変えたバーチ教授が、自分からわたし達に近づいて
「サチコ、ハゥ ハブ ユー ビーン?」(元気だったかい?)
「ベリー ウエル サンキュー、ドクター・バーチ」と幸子。
二年振りに我々はドクター・バーチとニューオーリンズの話や、チュレーン大学の友人や、秘書のルースのこと、また研究室の技術主任だったラルフや、黒人の研究助手だったワトソンの事などについて話を弾ませていた。
その時である。一人の品の良い中年紳士が、我々の座っているソファーに近づいてきて、ドクター・バーチに話しかけた。
「失礼ですが、バーチ教授でいらっしゃいますか?」
「そうですが」とバーチ教授。
「わたしは日本医科大学の木村栄一(故人)です。バーチ教授には初めてお目に掛かりますが、今度のシンポジウムで、ご一緒に座長をさせて頂くことになりました」
「そうですか。木村先生のことはよく存じております」
「恐縮です」と木村教授。
「ところで木村先生は、ドクター・タカシナをご存知ですか?」
「いいえ、初めてお目に掛かりますが」
「ドクター・タカシナは、わたしの所で4年間いてくれました」
「それは好都合です。いま通訳の方を探していたところでした。髙階先生はバーチ教授のところにいらしたのですから、今度のシンポジウムの通訳をお願いできないでしょうか?」
「わたしはまだ通訳の経験がありませんし、ご期待に沿える様なことは出来ないと思いますが」
と一旦、辞退したのだが、今度はバーチ教授が
「ドクター・タカシナ、やってくれないか?木村教授もおっしゃっているのだから。」
と、二人の日米を代表する教授に頼まれ、ついに通訳を引き受けることになった。バーチ・木村両教授が、座長を引き受けたシンポジウムでは、隣にドクター・バーチが座っていた事もあって初めての学会通訳もスムースに運んだ。シンポジウム終了後、木村教授から「先生の素晴らしい通訳、本当に有り難うございました」と丁重なお礼の言葉を頂いた。そのシンポジウムが終わった直後にアジア太平洋心臓病学会事務局から改めて依頼があり、結局、わたしはこの学会で六つのシンポジウムの通訳をこなしたのである。
この学会通訳が一つの契機となり、わたしは毎年多くの学会から依頼を受け、国際小児科学会などのシンポジウムの通訳も行った。当時は通訳でも医学関係のものをこなす人が少なかったが、或る大学教授の中には、わたしをドクターではなく単なる通訳に過ぎないと見下した態度を取った人が何人かいた。ある学会で演壇を降りたわたしに、
「君は通訳にしては、医学の内容を良く理解しているね」
と、尊大な態度でわたしに問いかけたある教授に向かって、木村栄一教授が、
「先生は髙階先生をご存じないのですか?彼はアメリカで勉強した心臓病専門医です」
と、厳しくその教授に向かって嗜めるような言葉を掛けたため、その教授がビックリした様にわたしを見つめ直したが、その仕草に反ってわたしが恐縮してしまったことがあった。しかし、わたしは学会での医学通訳を引き受けたことは、学生時代に金子先生から教えられたことに対する恩返しだと、心密かに思っていたので別に気にもしなかった。
(*そのバーチ教授は、1986年、急性心筋梗塞のため自宅で亡くなった。バーチ先生は、病院のICUに搬送されることを拒み、自分がいつも口にしていた「人は尊厳を持って生まれ、尊厳を持って死すべきものだ」という言葉を自ら守ったのである。)
13.恩師・金子敏輔先生
1969年、夏、わたしの人生にとって一つの転機が訪れた。「淀キリ」(淀川キリスト教病院)での外来診療の忙しさは格別であった。患者数も次第に増えていったが、ある日の事である。前出の金子先生から久し振りに電話が掛かった。
「髙階先生、ちょっとお邪魔していいかな?実は僕のレントゲン写真を貴方に診てもらいたいのだ。ここ2ヶ月程、咳が止まらなくってね。神戸大学内科で診てもらったのだが、貴方の意見も聞きたくってね。咳の原因が右下葉の気管支肺炎を起こしているためだろうと言う事だが、わたしの診たところでは肺炎ではなさそうな気がするのだ。悪性腫瘍の可能性もあるしね」
「そうですか、早い方が良いですね。先生、きょうの午後にお出で下さいますか?」
その日の午後、金子先生は病院へレントゲン写真と血液検査の結果を持って現われた。内科の第一診察室で壁に埋め込まれたビューワーに掛けた自分のレントゲン写真を見ながら、金子先生はわたしの言葉を待っている。
「先生、右の横隔膜の陰影は、どう見ても単なる肺炎ではなさそうです。しかし、必ずしも先生がお考えになっていらっしゃるような悪性腫瘍とも言い切れませんが」
「しかし、陰影の形が円形でもないだろう?」
「そうですね、やはり断層写真を取った方が良いと思います」
「是非、そうしてくれますか」
「すぐに放射線科の方に連絡しましょう」
と言って卓上電話を取った。
断層撮影が行われた結果、わたしが危惧していた通り金子先生の右横隔膜上に見えた陰影は腫瘍であった。悪性腫瘍の可能性があるかも知れない。この時、金子先生はすでに自分の病気のことを悪性腫瘍だと予測していたに違いない。
「いや、いろいろ先生にはお世話になったよ。どうやら断層撮影のお陰ですっきりしたよ」
と、淡々とした晴れやかな表情で話す金子先生の顔を見た時、わたしは、金子先生が人生活動を締めくくる重大な局面に差し掛かっていることを知った。
彼は笑いながら、
「人生って、何が起こるか分らないね。これからまだまだ遣らなければならないことが山ほどあるのにね」
と、自分にも言い聞かせるように笑いながら話し、しっかりした足取りで病院の玄関を出て行った。
かつてシカゴ大学医学部を卒業し、アメリカで外科医として活躍した後、神戸に帰り、第二次世界大戦中は欧米の捕虜の健康管理を行い、彼らに絶大な信頼を得たドクターである。戦後も駐留軍の顧問として働き、以後、全国の大学医学部で初めて神戸大学医学部に医学英語講座を開設し、初代の助教授となって医学教育のため活躍を続けてきた。その国際的な偉大な人物が、人生の終末を迎えようとしているのだ。何処となく寂しげに見える金子先生の後姿を、いつまでも見送っていた。
「先生、何時までも、お元気でいて下さい」と祈る気持ちだった。
しかし、それから一ヵ月後に金子先生の容態は急変し、右胸部の疼痛と共に呼吸困難が激しくなった。金子先生は友人の勧めに従って神戸大学医学部附属病院に入院した。彼の主治医になったのは、後輩の一人である小林克也だった。喀痰の組織培養検査で腫瘍細胞が検出されたが、小林は金子先生にその結果を告げなかった。わたし達は学生時代、共に金子先生によって医学英語を教えられアメリカに留学し心臓病専門医となったが、小林もまた内科全般に亘る専門医としての修練を積んでいた。しかし、わたし達が一番危惧していた通り、恩師・金子先生の右横隔膜上に出来た腫瘍の病理診断は「悪性多発性骨髄腫」であった。
金子先生は、やがて自らの死期が近いことを悟ったのであろうか。ある日、小林に向かって
「小林先生、済まないけれど淀川キリスト教病院の髙階先生に、時間があったら、僕のところに寄ってくれるように連絡してくれませんか?」
小林は早速わたしに電話を掛けた。そして翌日の午後、金子先生の病室を訊ねると、
「やあ、元気そうだね。忙しいのにお呼びたてして済まない」
「いいえ、どう致しまして。その後、お体の具合は如何ですか?」
「いやあ、余り変わらないね。ちょっと食欲が落ちた位だよ」
と口では言っているが、誰の目にも分るほど頬が落ち込み、体重も減り、昔は白人と間違われるほど肌の白かった金子先生の皮膚が、茶褐色に変わっている事に気付いた。金子先生は右胸の疼痛を鎮痛剤で押さえ必死に耐えながら、あえて元気そうに、
「髙階君、実は相談があるのだが」
その時、初めてわたしを「君」と呼んだ。
「何でしょうか?」
「僕も、余り長く大学の講義を休むわけには行かないと思うから、君にわたしの講義を替わって貰いたくて連絡したのだよ」
「でも、先生のような立派な講義が出来るかどうか、ちょっと不安です」
「いいや、君なら大丈夫だよ。淀川キリスト教病院での講義の素晴らしさや、アジア太平洋心臓病学会での名通訳振り、それに若いドクター達への指導の上手さは、素晴らしいと聞いているよ」
「しかし、先生の様に医学英語を教えるとなると、英語の勉強をもう一度しなければなりません」
「いやあー、心配要らないよ。君がチュレーン大学医学部で、心臓病について勉強してきた事を、学生達に伝えるだけで十分だ」
「それでは、アメリカで医学生達を指導してきたようにやってみます」
その時、金子先生の顔から微笑みが消え、両眼からどっと涙が溢れ出した。わたしは金子先生の顔を見たが何と言えばいいのか言葉が見つからず、一瞬詰まったようになり、声も出ず黙って両手を差し出すと、金子先生は両手をしっかりと握り締めながら
「有難う、髙階君、これで僕も安心したよ」
と言った後、じっとわたしの顔を見詰めた。その表情は、今までに一度も見たことのない金子先生の真剣な眼差しであった。
「金子先生、また参りますから、ご連絡ください」
と言い残して金子先生の病室を出たが、わたしは廊下で急に立ち止まった。後ろ髪を曳かれるような思いと、心の底からの悲しみが込み上げてきて、急に堪えきれなくなったのだ。
金子先生は、わたしが卒業直前に父親を亡くした時も、父の代わりになって励ましてくれた。そしてわたし達のために努力し、当時、米国陸軍病院を日本のインターン実習病院として認可させるため、厚生省に赴いてくれた事などが、つい昨日のことの様に思えた。また彼が久し振りにアメリカに旅行し、ニューオーリンズへ立ち寄った際、シカゴ大学医学部の旧友達との再会を報じた新聞を、わたし達夫婦のアパートで見せてくれた金子先生の元気だった姿や、久し振りにチュレーン大学のアパートで一緒に食べたすき焼きのことなども思い出された。わたしは涙に曇った目で暫く茫然と廊下に立ちすくんでいたのだ。
「どうかなさったのですか、先生?」
通りすがりの看護師が心配そうにわたしを見詰めて声を掛けた。
「いやあ、何でもないよ」
と言いながらハンカチで涙を拭き、気を取り直して病院の廊下を歩いていった。それから2週間目に金子先生は亡くなった。金子先生の生前の遺言によって行われた病理解剖には、「淀キリ」のフランク・ブラウン副院長も立ち会った。もう決して口を開く事のない偉大な人物「金子敏輔」がそこに横たわっている。
病理解剖の執刀医が金子先生を苦しめた右肺下部の「悪性多発性骨髄腫」が取り出された時、わたしは心の中で「金子先生、長い間、苦しかったことでしょう。どうかゆっくりお眠り下さい」と呟いた。金子先生がその苦しみから解放され、天国に旅立った事を改めて知ったのである。享年72歳であった。
「金子先生、さようなら。長い間、本当に有難うございました」
【・・・次回に続く】
※「わたしのパスかる」へのご感想をぜひお寄せください。 office@jeccs.org