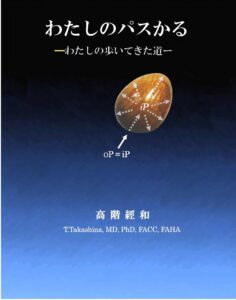ジェックスの設立者で理事長の髙階經和先生が、お生まれになった1929年から現在進行中の研究成果まで、90年を超える人生と研究をみずからまとめておられます。
内容はもちろん、読み物としても大変興味深い「自叙伝」となっています。ぜひお楽しみください! (連載内容の目次はこちら)
*****************************************************
『わたしのパスかる!』(連載第3回)
ーわたしの歩いてきた道ー
ジェックス理事長 髙階 經和
第二章:-1954年~1971年-
1.戦争外科に明け暮れた毎日
1954年5月当時、大阪府堺市には第382米国陸軍病院があった。第二次世界大戦中、日本の陸軍連隊があったが、戦後、米軍に接収され広大な連隊の敷地が第二次後送病院として最適な環境となった。木造の建物であったが、米軍病院になってから内装も一新され、近代的な設備の整った病院に生まれ変わった。真っ白な壁が広い庭の芝生と木立の緑に映えて美しい。そして病院のゲートには、何時ものようにMP(Military Police)が厳めしく警備に当たっている。
「ブルッ・ブルッ・ブルッ・ブルッ」と一機のヘリコプターが、我々インターンのいる将校宿舎(オフィサーズ・クオーター)の上を越え、病院の中庭にあるヘリコプター発着場に向けて飛んでいった。インターン生活を始めてから、既に一ヶ月が経っていた。
「また、また運ばれてきたか」インターンの一人、宮崎正夫が言った。暫くすると宿舎の廊下にあるスピーカーから呼び出しベルが鳴る。わたしは外科のローテーションが始まったばかリである。
「ドクター・タカシナ、リポート サージャリイ。」(Dr. Takashina, report to surgery. Repeat) (ドクター・髙階、外科に連絡ください。繰り返します。ドクター・髙階、外科に連絡ください)
「オーケー、分かったよ」とわたしは、スピーカーに向かって大声で答えながら、白衣を羽織って大急ぎに宿舎から飛び出して、宿舎から150メートルほどの距離にある病院の裏口まで一気に走り抜ける。入り口で警備兵の敬礼を受けて中に入る。2階の外科へ階段を二段とびで駆け上がる。大急ぎでブルーのスクラブ・スーツに着替え手洗いを済ませ、ナースが持っている手術用ガウンの袖に手を通し、両腕を肘で曲げ両手を挙げたまま、自動ドアを通って手術室に入る。呼び出しを聞いてから5分である。
やがてヘリコプターで運ばれてきた患者が、ストレッチャーで手術台に運ばれてきた。2人の男性の看護兵が患者を手術台に移動させた。ただちに麻酔医のドクター・シャーリーが麻酔を始めた。やがて軍医大尉で整形外科医のドクター・ダンカンが手術室に姿を現した。眼鏡の奥のギョロリとした目玉が光る精悍な男だ。
「グッド モーニング、キャプテン ダンカン」
「オーケー レディ」(用意できました)と手術室主任。
「サンクス」とドクター・ダンカンが答える。手術が始まった。素早く患部が消毒された後、ブルー・シーツが掛けられた。ドクター・ダンカンのメスが、患部を素早く切り開くと血が滲み出す。
「ヘモスタット」(止血鉗子)
「イエス サー」手術場のナースが止血鉗子を手渡す。ドクター・ダンカンのメスが金属の破片が食い込んでいる場所に近づいていく。手術室の壁に埋め込まれたレントゲン・ビューワーに掛けられた写真を見ながら、鮮やかな手さばきで、患者の大腿部に食い込んでいるほぼ三角形の金属片に近づいていく。幸い出血も少ない。
「もうすぐだ」と整形外科医のドクター・ダンカンが鉗子で金属片を取り出し、キドニィ・ベーシン(腎臓型の膿盆)に入れた。「カタッ」と小さな金属音を立てて、砲弾の破片が取り出された。
「オーケー、ウイ ガット イット」(取り出したぞ)
その後、血管を再縫合し創面を洗浄して皮膚を縫合し手術が終了した。
毎日、ヘリコプターで運ばれてくる傷病兵の多くは、朝鮮戦争の前線から福岡にあった米軍病院に移送され、応急手当が行なわれた後、再び福岡から大阪伊丹空港へ、更にヘリコプターでこの病院に搬送されてきたのだった。しかし、彼等は戦傷を負ったにも拘らず意外に陽気で明るい。中には、手術の後、病棟を抜け出してアメリカ将兵慰問隊のダンスに行ったため、縫ったばかりの傷口が裂け、再手術となった馬鹿がいた。ダンカン大尉が顔面を真っ赤にして、その兵士を仁王のような顔立ちで睨みつけ叱り飛ばしていた。
「貴様は馬鹿か!」「イエス サー」真っ青になって震えている兵士は、ダンカン大尉の顔を見詰めたまま、「イエス サー」を繰り返していたが、それしか言えなかったのだ。
「信じられんな!」ダンカン大尉にしてみれば、「折角、手術で治してやったのに、何たる奴だ」と怒るのも無理はない。わたしは彼等の外科手術に立会い、「この先、彼らは傷痍軍人として、社会に復帰していけるのだろうか?」と彼らの前途に不安を抱き、当時の日本の病院でインターン生活を送った大学時代の仲間には、到底想像できなかった様々な戦争外科を体験したのである。しかし、病院に勤務した当初、学生時代には外科手術などには立ち会ったこともなかったので、
「君は縫合の練習が必要だ!」悔しい。「日本の大学では医学生が手術室に入ることは許されてもいなかったし、知らないのは当り前じゃないか」と、いったところで始まらない。しかし「馬鹿にされてたまるか」と反骨精神を全身に漲らせる。
毎晩、手術室では不要になった針と鉗子を、手術室の看護婦のナンシー中尉からもらい、毛布を使って必死に縫合の練習をした。その甲斐あってわたしの縫合技術は短期間で一気に上達した。それに伴い手術も段々面白くなり、骨折手術後の皮膚縫合を毎日、何回となく経験していった。手術が殆ど終りに近づくとドクター・ダンカンが「ドクター・タカシナ、ドウゾ」「イェス サー」。わたしは手際よく縫合を始める。その甲斐あってドクター・ダンカンから「ドクター・タカシナ、君は将来、良い整形外科医になれるぞ」と言われ、自分も整形外科医に向いているなと考え始めていた。
この病院で出会った若いドクターたちは、何れも殆どレジデントを終わったばかりか、またレジデントの修練期間中、徴兵軍医になった人たちが多かった。また彼らは絶えず積極的であり非常に勉強熱心であった。ラウリー軍医少佐(Major Dr. Lowley)から、わたしと一緒に大学の同級生だった富永周作君と共に心電図の講義を聞いたが、アメリカ人独特のジョークを交えながらの話しに大学時代には聞いたことのない新鮮さを覚えた。心電図に興味を持ったのはこの時である。何よりも軍医の多くが若く、それに医学的知識の豊富さに加えて、勉強熱心でありまた我々インターンに対する紳士的な態度に少なからず驚かされた。
【・・・次回に続く】
※「わたしのパスかる」へのご感想をぜひお寄せください。 office@jeccs.org