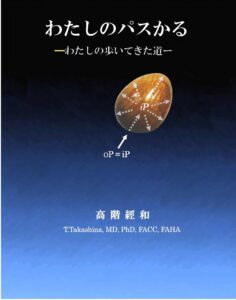ジェックスの設立者で理事長の髙階經和先生が、お生まれになった1929年から現在進行中の研究成果まで、90年を超える人生と研究をみずからまとめておられます。
内容はもちろん、読み物としても大変興味深い「自叙伝」となっています。ぜひお楽しみください! (連載内容の目次はこちら)
*****************************************************
『わたしのパスかる!』(連載第2回)
ーわたしの歩いてきた道ー
ジェックス理事長 髙階 經和
第一章:-1929年~1954年-
1.人生とは四つの時期で成り立っている?
日本人の寿命は現在長寿男性81,64歳、女性87,78歳となり、「人生百歳時代」という人もいる。しかし、単純に人生を25年単位で割ることは難しい。一般的に人生を四つの時相で分けて見ると「少年期」「青年期」「実年期」「老年期」に分けられる。現実には、少年期が長い人や、青年期が長い人もいるが、その逆もある。若いはずなのにアッという間に老け込んでしまう人もいる。
それを見事に『青春という名の詩』に謳ったのは、アメリカ南部の詩人「サミュエル・ウルマン」だった。「青春とは人生のある時相を指すのでなく、心の持ち方を言う(中略)逞しい意思、豊かな想像力、燃えたぎる情熱をさす。(中略)20歳の青年よりに60歳の人に青春がある。年を重ねただけで人は老いない。(中略)歳月は皮膚にしわをますが、情熱を失ったとき、人ははじめて老いる」・・1990年、本書をもとに書かれた同名の著書をわたしは当時、関西経済連合会会長だった宇野収氏から頂いた。それ以来、『青春という名の詩』はわたしの座右の銘になっている。
わたしの少年期は昭和一桁生まれの方々と同様、戦争を体験したことになるが、自らの少年時代を振りかえって話す人々が少なくなってきた。今や社会の中枢を占めている方々は第2次世界大戦後生まれである。戦時中の国民生活はテレビドラマや、ドキュメンタリー番組を通して紹介されているので想像することは出来るが、ニ度とあのような生活は経験したくないというのが、偽らざるわたしの気持ちだ。
よく考えて見ると、人生は年齢や環境により社会的貢献度が異なる、全ての職業の優劣を単純に表すことは難しく「人生の充実度」(Quality of Life=QOL)を評価することはできない。自ら満足のいく人生を歩み、社会に貢献した時に人生の価値が決まるからだ。人生とは簡単に四分割できないものだと考えている。
2.父が脳出血で倒れた
わたしは1929年生まれで、四人姉兄の末っ子である。わたしが幼い頃、かなりのヤンチャ坊主であった。父は戦争中大阪北区で内科医として木造二階建ての家で自宅開業していたが、父が一階の診察室で診察している最中にわたし達兄弟が二階の部屋を走り回ったので、父に酷く叱られたことがある。しかし戦時中、父は近隣地区の警防団団長に推薦され、診療が終った後も警防団団長の仕事をしなければならず、体力的にも精神的にも無理をしていたに違いない。
或る日、父は往診先から帰るなり「今日は疲れた」と言って風呂も入らずに布団に入った途端、急に意識がなくなり大きな鼾をかきだした。母は驚いたが、すぐに父の友人である内科医に往診を頼んだ。その先生は、父を一目見るなり「髙階君は助からないかもしれない」「・・・・」母は暫く無言だった。49歳の冬「右側脳出血」であった。母はその瞬間、大声で泣いた。わたし達子供の前では決して泣かなかった母が大粒の涙を見せた。子供心にも大変なことになったと感じた。
しかし父は3日目の朝うっすらと目を開いた。母はどんなに嬉しかった事だろう。その喜びはわたし達子供にも伝わった。それから一年半、わたし達は岸和田にある小母の家に預けられ、そこから毎日、大阪城追手門の前にある偕行社尋常小学校まで通った。そして姉の友人の紹介で阪神甲子園線「高砂」駅前にある一軒家を借りることが出来、わたし達は1年半ぶりに家族は再会を果たした。あの時の喜びはいまも忘れことができない。父は左半身不随の身となったが、その後、母が父の右腕となって働き何とか自宅で診察が出来るまで回復した。戦時中の食事はイモの葉っぱや、大根の葉っぱ、偶にジャガイモの入った雑炊が主食であった。どんな家庭でも白米を食べることは出来ず、米は配給制で家族の多い家では主婦は家族のために如何に食べ物を手に入れるかに明け暮れた。
3.第2次世界大戦勃発
やがてわたしが小学校5年生になった時、日本海軍は1941年 12月8日、ハワイのオワフ島に集結中の太平洋艦隊に奇襲攻撃を仕掛け、また陸軍は マレー半島コタバルに上陸した。日本陸軍が真珠湾攻撃より1日早く英守備隊と交戦、翌日には市内を占領した。こうして第2次世界大戦の幕が切って落された。ラジオで報道される大本営発表は日本の勝利を伝えていた。
しかし戦争が3年を超えた頃、わたし達中学生も勤労動員という名のもとに陸軍の砲兵工廠で働かされた。戦況が悪化し敗戦濃厚となった。わたし達が働いていた砲兵工廠を米軍の艦載機が機銃掃射で襲いかかり、砲弾を運んでいた友人の1人が目の前で銃撃され即死した。道路が真っ赤な血で染まった時、ショックは余りにも大きく、わたしたちは凍り付いた様にその場に立ちすくんだ。
その日の夕方、家に帰ったわたしは母に今日目にした出来事を話したが、母は悲しげな表情を浮かべ聴いていた。「お母さま、僕も明日は艦載機に打たれるかも知れないよ」と言ったところ「どうかそんなこといわないで!」と泣き出さんばかりの表情でわたしの手を取り、拝むように懇願した。その翌朝、空襲警報がなった直後、わたしは半身不随の父を助けて庭に作った防空壕に退避した。その数秒後である。急にバリバリと音を立てて艦載機が機関銃でわたし達の住んでいる住居を襲った。空襲警報が解除されたので防空壕の扉を開けて目にしたものは、診察室の窓枠を突き破り、銃弾が反対側の壁にめり込んでいた光景であった。しかし不思議に恐怖心が沸かなかった。東京、名古屋、大阪などの日本の主要都市をはじめ日本全土が連日空襲に晒されていたが、最後に1945年8月6日、広島に原子爆弾が投下され、続いて同年8月9日に長崎にも原子爆弾が投下された事で日本は戦意を失った。
そして1945年8月15日、終戦を迎えた。ラジオを通して天皇陛下の玉音放送があり、初めて日本が戦争に敗れたこと事が国民に知らされた。戦争中、毎日大本営発表のニュースは日本陸海軍の輝かしい勝利への道を歩んでいたというニュースとは裏腹に、現実は全く反対であった。わたし達がいままで教え込まれた価値観は一変した。学校に出て最初にしたことは、小学校時代や中学校で習った歴史の教科書を墨汁で塗りつぶす作業だった。「今まで習った日本歴史は過ちだったのだろうか?」というのが偽らざる感想である。同時にわたし達の考え方を転換しなければ世の中の動きについていけないという不安に変わっていった。
4.神戸医科大学への道
1948年3月から3年間、わたしは丹波篠山にあった兵庫医科大学予科での寮生活を終え、1951年3月、大学医学部に進学することが出来た。その頃に朝鮮戦争が始まったのである。兵庫医科大学は神戸医科大学と名称を変え、そして戦争終結後に神戸医科大学医学部になったが、神戸医科大学を国立の神戸大学医学に昇格させた陰の功労者が金子敏輔先生であった。わたしの大学生活での授業の大半は医学英語の勉強に使われたと言って良い。
当時、先任講師であった金子先生は、戦争前にシカゴ医科大学外科に勤務し、戦争が始まる前に神戸に帰国した。金子先生は「吉田松陰」と共に千葉県下田港に停泊中のアメリカ軍艦に乗り込み、渡米を図ろうとしたが投獄され獄中死した「金子重助」の甥にあたる。金子先生は叔父の意思を果たそうと決意し、1910年に単身アメリカに渡り、高等学校から医学の道を選び、シカゴのロヨラ医科大学を卒業した。そして外科医となり、数年、アメリカで開業していたが、日米関係が不穏な状態になったため、神戸に帰国し神戸在住の外国人のためにクリニックを開いた。
戦後、神戸医科大学学長の「正路倫之助」先生は、医学教育には英語が欠かせないと考え、日本で初めての医学英語講座を開設し、金子先生を専任講師として迎えた。先生は殆どネイティブのアメリカ人の様な発音でわたし達学生に医学英語を教えた。そしてわたし達は自主的に英語会話クラブを立ち上げ、わたしが初代のキャプテンとなった。金子先生を通して垣間見たアメリカの医学レベルの高さと、国際的に高い評価を受けている「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン」(New England Journal of Medicine)を学部の一年生の時から読み始めたことが、わたしを大きく変えた。これからの時代はドイツ医学ではない。アメリカ医学が主流となる「よし、将来は絶対にアメリカに行って勉強しよう」と密かに心に決めたのである。
5.父危篤の知らせ
1953年11月10日、大学の卒業試験直前の事である。戦争中に起こした脳溢血のために父は段々と体力が衰えていた。そしてわたしが講義を受けている時、大学事務局の職員が講堂に急ぎ足に入ってきた。職員は公衆衛生学の松島教授に何やら話していたが、急いでわたしの名前を呼んだ。すぐに松島教授が
「髙階君」「はい、髙階ですが」
「髙階君、お父様の容体が悪くなられたので、急いで帰って下さい」
「はい」と返事し既に覚悟はしていた心算だったが、ぐっと胸が詰まる思いが込み上げてきた。「お父様、僕が帰るまで、待っていてください」大急ぎで神戸三宮駅から、阪神電車に乗って甲子園でおりた。甲子園線で「高砂」駅で降りて走った。そして自宅の玄関から父のいる部屋に急いだ。 襖を開けると、父は床に横たわったままわたしが帰るのを待っていたように、わたしの顔を見つめて軽く二度頭を振った。そして父は静かに息を引き取った。満64歳であった。母は大声で泣き崩れた。気丈な母が病身の父を抱えて、わたし達子供のためにどれ程頑張った事だろう。 同日、父の遺言で大阪大学で行われた病理解剖には、わたしと兄の経昭が立ちあった。父の解剖を視るのは本当に辛かった。まるで自分の身を切られている様で、それが「病理解剖を受ける事になった患者の家族の気持は、どんなものかを知らなければいけない」という父からわたし達へ最後の教えであったと今でも思っている。父の死で精神的にわたしは強くなった。1954年3月3日、わたしは神戸医科大学を卒業し、すぐにインターン生活が始まった。
【・・・次回に続く】
※「わたしのパスかる」へのご感想をぜひお寄せください。 office@jeccs.org