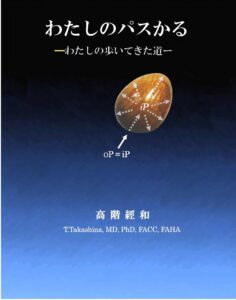ジェックスの設立者で理事長の髙階經和先生が、お生まれになった1929年から現在進行中の研究成果まで、90年を超える人生と研究をみずからまとめておられます。
内容はもちろん、読み物としても大変興味深い「自叙伝」となっています。ぜひお楽しみください! (連載内容の目次はこちら)
*****************************************************
『わたしのパスかる!』(連載第9回)
ーわたしの歩いてきた道ー
ジェックス理事長 髙階 經和
第二章:-1954年~1971年-
17.臨床における三つの言葉
「心エコー図は、まだまだこれからの学問だし、新しい診断法として確立されるのには、もう少し時間がかかるだろう。しかし、わたしが学んだ『心電図学』は、1903年にオランダの物理学者だったアイントーフェンが最初に考えついたものだ。すでに一世紀が経っているが、心電図とは心臓が1心拍毎に発している電気生理的な変化を記録して、これを心臓病の診断に応用しているのだ。つまり心電図とは、心臓の電気生理的な言葉なのだ。言い換えて見ると『臓器の言葉』(organ language)というわけだ」
「臓器の言葉って、初めて聞きました」と、ある学生が言った。「これは、1969年に、クリーブランド・クリニックのアーヴィン・ページ教授(Dr. Irvine Page) が、『心音や心雑音、そして呼吸音や腸内雑音などを、臓器が発する言葉だ』と、医学雑誌に書かれたことがある。すでに、ページ先生はその時、新しい医療診断機器が次々に開発されたため、ヤング・ドクターがこれらの機器を使って診断するのは、完全に患者さんを診察した上でなければ決して初めから使ってはいけない、と警告しておられたのだ」
最近では患者さんから病歴も聞かず、十分な診察も行わずに、いきなり検査する若い医師が何と多いことだろう。それに患者さんに対して納得のいく説明も出来ない医師がかなりいる。
「君達が患者さんから主訴や病歴を聞くだろう?それは『日常語』つまりspoken languageだよ。そして身体所見は『身体語』でbody language という事になる。だから臨床の言葉には三つのものがあって、その三つの言葉が理解できなければ、臨床医とは言えないよ」
この『臨床の言葉』(clinical language)とは、わたしの造語だが『三種の神器』ならぬ『三種の言語』である。学生達の中には深く頷いているものもいた。わたしは学生にプレテストとして様々なベッドサイド診断教育用のスライドを作っておいた。
「これからわたしが二枚ずつスライドを使って、そのどちらが正しいかを諸君に言い当ててもらおう」
と言ってわたしは頚静脈波の診かたや、全身の動脈波の触れ方、心尖拍動の触れ方や、聴診のしかたなどの基本的な臨床手技を「正解」と「誤り」の2枚のスライドを学生達に示していった。彼らは初めどれが正しいのか分らなかったが、わたしが「正・誤」を解説するに及んで、その教育法に興味と関心を示し始めたのである。
1969年より、17年間に亘って神戸大学医学部で教鞭をとったが、その間色々なことがあった。講義を始めて5年が経過した頃に、教授会でわたしの講義が臨床心臓病学を中心としたものであり、学生の人気も高かったためか、教授会は「髙階先生の医学英語の講義は,基礎的知識として極めて大切であり、ぜひ学部1年の学生から教えて頂きたい」と結論を出したが、それには裏があったのだ。その裏とはわたしの講義に対して、ある教授から「何も心臓病の講義をしてもらわなくても結構だ。髙階先生は英語だけを学生に教えれば良いのではないか」と反対の意見が出されたことを、後輩で友人である基礎の教授から聞かされた。
その後、その教授はわたしを部屋に呼びつけ同じ文句を言ったのには、呆れてものが言えなかった。わたしは件の教授の教室員ではない。それに5年前、わたしが講義を始めた時には、「髙階先生、ぜひ臨床の話を学生たちにしてやって欲しい」と言ったのは、他ならぬ彼だったからである。その教授も最早、故人となった。
わたしはいつもの通り、朝8時30分から1年生に医学英語の基礎的なことから講義を始めたが、医学には全く素人である低学年の学生には、わたしの講義は「馬の耳に念仏」であったに違いない。戦後の高度成長期に育った若者達には、ハングリー精神が欠けていた。それに「今更、髙階先生の言うようにアメリカに行かなくても日本で十分やっていけるじゃないか」というイージーゴイングな気分が、すでに学生の間に蔓延していた。それに加えて日本全国の大学に広がった学園紛争のため、大学の授業も暫らくの間、休講となったのである。一方、わたしの講義が無くなったことに酷くショックを受けていた3年生の一部の学生達に対してある提案を行った。
「君達、もし休み中にわたしのクリニックで勉強したかったら、2〜3人ずつ、二週間交代で来てみるかい?」
「はい、ぜひ先生のクリニックに行かせて頂きます」
と、彼らは顔を紅潮させて答えた。こうして夏休みや、春休みを利用してわたしのクリニックで小グループの学生たちに対して実地の臨床実習を始めたのである。診察室では
「僕は神戸大学3年生の前川といいます。この二週間、先生のところで、実習させて頂いております。宜しくお願いします」
「こちらこそ宜しく」と患者さんが答える。それは事あるごとに「諸君はドクターである前に、一人の社会人として誰に対しても礼儀正しく接するべきだ」と話していたからである。毎日の実習に来た学生達には各自に10枚の心電図を渡し、それを自分の力で読ませた。大学では数時間の講義しか受けていない学生達にとって、毎日提供される心電図を目の前にして緊張していた。
「前川君、君読めるの?」と相棒の学生が聞く。「いーや、僕はまだ心電図の本を読み出したばかりだ。さっぱりだよ」とその学生が答える。他の仲間が心電図を読んでいる間に、わたしは一人の学生を診察室に招き、診察の順序を頚静脈波の診かた、全身の動脈拍動の触れ方、心尖拍動の触れ方、聴診の仕方から手にとるようにして教えていった。患者さんに向かって「学生さんのために聴診をさせて頂きたいのですが、宜しいですか?」と断った上で、聴診の実習を始めた。
「分かるかい?この3拍子リズムの最初の小さな音が4音なのだ。4音は心房が収縮した時に血液が左心房から左心室に流れ込んで、心尖部を打つときに発生する音で、自分の片方の手を耳に近づけて振った時に、耳に感じる風のような小さな音だよ」
「誰でも聴こえるのですか?」
「高齢者の方では約半数に聴くことが出来るし、心筋が硬くなる動脈硬化性心疾患(老人性変化によるもの)や肥大型心筋症(原因はまだ不明である)の場合でも聴こえるのだ」
「・・・・・」
「これが聴診の始まりだ。最初は誰でも4音は聴こえない。しかし、確かにそこにあるという事を知って聴診するのと、知らないのでは大きな開きがあるのだ。もう少し時間を掛けて聴いてごらん。必ず聴こえる様になるから」
その翌日、別の患者さんの心音を聴いていた杉本君が感激したように言った。
「あっ、先生、分りました、4音の小さな音が聴こえました」
こういったやり取りの後、わたしが毎日、新しい診察法について、一人ずつ学生達に教えていった。彼らは大学では決して教えてもらえない臨床診断の手技をわたしから学んでいったことだろう。
18.ハーヴェイ教授との出会い
1971年10月、首都ワシントンの郊外、メリーランド州ベセスダ市の閑静な住宅地にアメリカ心臓病学会は、事務局本部と心臓病研修センター「ハート・ハウス」を完成させた。その完成を記念して3日間に亘って行われた杮落としのセミナー『ベッドサイドにおける心臓病患者の診かた』に、わたしは日本から唯一の参加者として出席した。特別研修センターは69席のジェット機のファースト・クラスを思わせる人間工学的に設計された椅子。その椅子には、電子聴診器をはじめ、LLシステム、講師と参加者がマン・ツー・マンで対話のできるオーディオ・システムなど、当時日本では考えられなかった程充実した「世界最高のクラスルーム」に、わたしは深い感銘を受けた。それよりもわたしを驚かせたのは、その69席の椅子の背中に、それを寄付したアメリカの各大学の有名教授の名前が刻まれていた事である。
このセミナーを主宰したのは、既に世界的に有名で「マスター・ティーチャー」(全米では医学教育に貢献した数少ない教育者に与えられる称号)を持つ、ジョージタウン大学医学部のプロクター・ハーヴェイ教授(ニックネームは「プロク」であった。わたし達が座っている特別会議室にベートーヴェンの「皇帝」の荘厳なメロディと共に会場に姿を現わしたのは、白髪の小柄な紳士である。彼こそがハーヴェイ教授であった。静かに話し始める。
「皆さん今回の「ハート・ハウス」の杮落としのこのセミナーによく参加して頂きました。わたしは主宰者として嬉しく思います。ところで、皆さん、このオーケストラで、いま演奏されている楽器の名前を当てることができますか?このメロディの中には、様々な種類の楽器が含まれています。それぞれの楽器の種類を聞き分ける耳を持つこと、これが聴診の始まりなのです」
そして始まったハーヴェイ教授の、あらゆる心臓病に聴かれる正常の心音や、各心疾患における心雑音を、口真似で表現する心音擬似法(Cardiophonetics)の素晴らしさ、そして時には、透き通ったクラリネット奏者の音色が会場一杯に響き渡ると、
「マイク、誰だったっけ?ニューオーリンズから来たあの男は?」
「ピート・フォンテンですよ。プロク(Prof. Proctor Harvey)」
と、彼の弟子で、現在マイアミ大学医学部のマイケル・S・ゴードン教授が笑いながら答える。そのクラリネットの音色を聞かせながら、会場に笑いを起こさせるハーヴェイ教授の華麗で、洗練されたスマートなショーマンとして、心憎いばかりの講義の進め方を見るにつけ、わたしは深い感銘を受け「どうすればハーヴェイ教授のような教え方が出来るだろうか?」と羨望にも似た気持ちを覚えた。休みなく語り続けるハーヴェイ教授の姿に、わたしは医学教育に賭ける「マスター・ティーチャー」の真面目を見た。そしてゴードン教授らチームが、作り上げた心臓病患者シミュレータ「ハーヴェイ君」(Harvey Jr.)を見るに及んで、思わず目を見張ったのである。
そのシミュレータとは、人体と等身大のシリコンゴムの表皮で出来たマネキンであり、頚静脈波、頚動脈波をはじめ全身の動脈波や心尖拍動を触れることが出来た。そして腹式呼吸もしている。聴診もシミュレータに具備した聴診器を使って聞く事ができた。わたしがずっと頭に描いてきた、ベッドサイド診断を教えることが出来る心臓病患者シミュレータを、目の当りにしたのである。「これこそ臨床教育に必要なものだ」わたしの心は大きく膨らんだ。
このセミナーが契機となり、「日本にもハート・ハウスのような研修施設を作りたい。そしてハーヴェイも導入したい」と夢を描いた。帰国してから、わたしの臨床教育に賭ける情熱に一段と拍車が掛かったのは言うまでもない。臨床の現場で診察の傍ら、医学生や看護婦達を教える事を決して厭わなかったし、むしろ積極的に自分の経験したことや考え方を披露した。
カラー・スライドで撮ってきた「ハート・ハウス」の内容を、わたしは依頼された講演のリハーサルを兼ねて、自宅で家内の幸子や、長男の経幸、そして次男の経啓を前に一生懸命に話した。まだ10歳と8歳の小学生を前に話をしたのだが、まだ小さな彼らには、随分迷惑なことだったろう。しかし「父親をあんなにまで興奮させるほどの事柄とは、きっと大変なものに違いない」と思ったと、次男の經啓が最近になってから話してくれた。
「ベッドサイドにおける心臓病患者の診かた」について話すわたしのユニークな講義の評判は、瞬く間に全国に広がった。その結果、各地道府県の医師会から講演の依頼が相次ぎ、殆ど毎月の講演で北海道から沖縄まで飛んだ事もあった。しかし、わたしがどんなに工夫して作ったスライドや、音楽や、心音聴診テープを使って研修を行って見ても、実際の心臓病患者を診察して臨床診断に至る過程や、心臓病患者の示す身体所見を「ハーヴェイ君」の様に表現できないという、もどかしさがあった。
ベッドサイドで一番大切なのは、何と言っても聴診である。その聴診の訓練のためには、まず「ハーヴェイ君」のように、人体と実物大のマネキンを作る必要がある。そして、マネキンにスピーカーを埋め込み、心音・心雑音を記録したカセットテープの音を、スピーカーから再現すれば良いと何時も考えていた。まず、その計画に必要な聴診用のマネキンを、どうやって作りだすか?また心音・心雑音を再生するための装置をどう作り出せばいいのかという具体的方法について案を練っていたのである。
【・・・次回に続く】
※「わたしのパスかる」へのご感想をぜひお寄せください。 office@jeccs.org