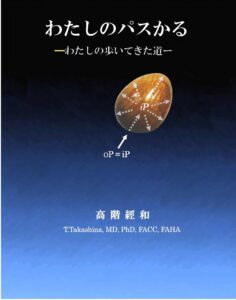ジェックスの設立者で理事長の髙階經和先生が、お生まれになった1929年から現在進行中の研究成果まで、90年を超える人生と研究をみずからまとめておられます。
内容はもちろん、読み物としても大変興味深い「自叙伝」となっています。ぜひお楽しみください!
*****************************************************
『わたしのパスかる!』(連載第14回)
ーわたしの歩いてきた道ー
ジェックス理事長 髙階 經和
第三章:-1980年~1994年-
11.心臓患者シミュレータ製作開始
わたしは、大洋工芸の安田修身主任に改めて、今度は「聴診シミュレータ」ではなく、新しい「心臓病シミュレータ」を制作する計画を話した。安田氏は全身のマネキンを作成する前に、脈波を発生させる装置を開発するため、マネキンの片腕を提供してくれた。そしてマネキンの手首の撓骨動脈の部位に、血管の拍動が触れるように幅1センチ、長さ5センチの穴を開け、ここに直径5ミリほどの生ゴムを入れた。これに清水氏が開発した電空装置(電気的にコンピュータの指示により、空気圧を変えることが出来る装置)を使って実験が開始された。
しかし、人体の通常血圧である120ミリメートル水銀柱の圧力を加えても、生ゴムで出来た人工血管はびくとも動かない。
「清水先生、全く脈が触れませんね」
清水氏もその部位を触れてみたが、心臓に見立てたポンプから送り出される圧では、生ゴムの壁があまりにも硬過ぎるのである。
「もう少し、上げてみましょうか?」と清水氏。しかし、圧が2気圧の240ミリメートル水銀柱、3気圧になっても「生ゴム血管」には、脈が僅かしか触れてこない。4気圧の360ミリメートル水銀柱になって、初めてわたしの指先に脈拍が触れ始めた。
「やっと触れた!」と、思わず清水氏は言ったものの、
「しかし、これでは大動脈の壁さえ裂けるほどの圧力ですよ」
「これでは実用では使えないな」とお互いに顔を見合わせる。
何度かのテストの繰り返した末に血管壁の材質を変え、ついに清水氏が辿り着いたのは、薄いシリコンチューブだった。これならば使える。そして電空装置を起動させると、120ミリメートル水銀柱のポンプ圧で十分に脈波が触れることが分かった。1988年春のことである。
清水氏の電空装置が完成したが、しかし、この新しい装置はサイズも大きく、まだどこの大学や病院でも実際に使えるようなものではなかった。
「ここまで完成しましたが、実践には役立ちませんね」とわたし。
「確かに、我々の工学部的な技術では、脈波を発生させることは出来るのですが、商品化するのには時間がかかりそうです。髙階さんも一度どこか、この装置に興味を示しそうな所に、声をかけてみられたらどうでしょうか?」と、清水氏は提案した。
「やってみましょう」
しかし、わたしの頭の中では、まだどうやってこの装置を実用化し、血圧発生の原理や脈波の形などを教えていくかについて、具体的な計画は立っていなかった。以前に清水氏がわたしに聞いたことがある。
「血圧や脈圧などは、測定し記録も出来るでしょう?」
「ええ、そうですよ」
「では、どうして、改めて人工的に血圧を発生させ、脈を作り出す装置が、必要になるのですか?」
「それは、現在の大学医学部での臨床教育では、血圧測定に始まり患者の脈をとるという教育が行われていないからですよ」
「しかし、我々専門外の人間から見ると、そんな基本的な診断技術は、お医者さんになる前に、みんな修得しているものだと思っていました」
「いや、事実はそうではないのです」
「それは、寂しい話ですね」
こういった話は、わたしが東京工業大学に清水氏を訪ねる度に交わされたものだった。まだ何処の大学でも臨床におけるベッドサイド教育が十分行われていない。ハイテクに溺れて、臨床におけるベッドサイド診断学の基本となるべき手技を、学生たちに伝えなければ、いまの教育方針のままでは、医学部教育は「医師」(physician)を育てているのではなく、単なる「医療技術者」(medical engineer)を作り出しているのではないか。
臨床心臓病学教育に対する、わたしの姿勢は変わらなかった。絶えず「どう教えるべきか」(how to teach)という事と、「どう教えてはいけないか」(how not to teach) という事を念頭に、講義を通していつも医師やナース、医学生達に問いかけていた。
それからわたしは学生たちにとって、最初に覚えてもらいたい心音として「機能性雑音」(無害性雑音とも呼ばれるが、10歳以下の子供であれば、約九割近くの子供に聴く事ができる雑音で、全く正常である)の聴診をさせて見た。
「分かるかい?“ダ”というⅠ音の後に、柔らかい“ハッ”という音が聴こえるだろう?良く聴くと“ダッ・ハッー・タッ”と聴こえるよ」
暫く学生の一人が聴いていたが、
「先生、小さな音ですか?」
「その小さな音が、人によっては大きく聴こえる事もある」
「でも機能性雑音か、どうかは、どうして判るのですか?」
「いい質問だね。機能性雑音というのは「三つのS」つまりShort, Soft, Systoleの頭文字を取っていうのだが、“短く、柔らかで、収縮期に聞かれる雑音”だよ。初心者にとっては、初めのうちは耳に聴こえないような音だね。聴診で難しいのは、心音の聴診であって、心雑音の聴診はむしろ簡単なんだ」
「はい」と答えてはいたが、まだ本当に分かったのかどうか疑わしい。それでも良い。学生たちが徐々に一つの診断技術を身に付けていけばいいのだから。
「大学の講義でも、何回も話したと思うが、自分が聴診した心音・心雑音を口で表現する方法を、「心音擬音法」(Cardiophonetics)と言って、アメリカのジョージタウン大学医学部のハーヴェイ教授(Prof. Proctor Harvey) が、その道の達人だよ」
「面白そうですね」と学生の一人が言った。
「心音や心雑音とは心臓が話す『臓器語』(organ language)。心電図も心臓の『電気的な言葉』だよ」
「先生の講義で、お話になる『心電図』も臓器語なのですか?」
「その通りだよ。心臓は一心拍毎に電気生理学的な変化を、我々に教えてくれているのだから」
「心臓病学って、興味がありますね」
「そうだ。心臓は一心拍毎に、我々に語りかけている」
学生達も徐々にではあるが、臨床心臓病学に興味が湧いてきたようであった。
12.アジア・ハート・ハウス構想と『スピリット』
1990年11月21日、わたしは「アジア・ハート・ハウス」構想を打ち出し、大阪府、大阪市、関西経済連合会、大阪商工会議所をはじめ、日本医師会や大阪府医師会、の承認を取り付け、いよいよ募金活動に入った。そしてアメリカ心臓病学会から歴代の会長であるリチャード・コンティ、ウイリアム・ウィンタース、そして事務総長のウイリアム・ネリガン氏を招いて記念講演を行うと共に、当時の大阪府知事・岸晶氏を訪ねた。
1971年にアメリカ心臓病学会の本部である「ハート・ハウス」の杮落としのセミナーに出席した事が、契機となって日本にも是非このような素晴らしい医学教育センターを作りたいと思い、「アジア・ハート・ハウス」構想を提唱したのである。日本は当時、バブル景気の真っ最中にあり、そして関西国際空港の開港を目指して産官学あげて国際化への熱い思いが広がっていた。
わたしは各製薬企業をはじめ、一般経済界の各団体を訪問し募金を依頼した。どこの企業も最初の訪問では賛成の意思を表したかに見えたが、2度目の訪問では、本論賛成、各論反対の態度をみせ、募金も思うようには進まなかった。それでも2~3の大企業から多額の浄財を寄付して頂いたことが、どれほどわたしの心の支えになったことであろう。何度も大蔵省や厚生省を訪れ、アジア・ハート・ハウス設置の必要性を提言したが、殆ど進展は見られなかった。中には「ハート・ハウスはどうなった?」とわたしに対する中傷じみた言葉を直接,間接に耳にする日が続き、思うようにことが運ばず切歯扼腕の日々が続いていた。その頃、大阪府国際交流監であった大藤芳則氏が関西国際空港建設に当たって活躍した事や、大藤氏が積極的に国際的医学教育センターの設置に賛同し、彼との交流をわたしは『スピリット』という題名で集英社から出版した。関西国際空港の舞台裏と、アジア・ハート・ハウス設置へのわたしの活動を描いたのである。これが第-7「パスかる」である。(6)
【・・・次回に続く】
※「わたしのパスかる」へのご感想をぜひお寄せください。 office@jeccs.org