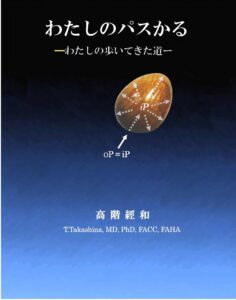ジェックスの設立者で理事長の髙階經和先生が、お生まれになった1929年から現在進行中の研究成果まで、90年を超える人生と研究をみずからまとめておられます。
内容はもちろん、読み物としても大変興味深い「自叙伝」となっています。ぜひお楽しみください!
*****************************************************
『わたしのパスかる!』(連載第10回)
ーわたしの歩いてきた道ー
ジェックス理事長 髙階 經和
第三章:-1980年~1994年-
1.アメリカ心臓病学会フェロー(FACC)となる
1980年3月、大阪国際空港からサンフランシスコ行きのユナイテッド航空810便で、わたしは妻の幸子と共に午後6時30分に飛び立った。眼下に見える卵形の大阪湾の漣が夕陽に映えて茜色に輝いている。空から見る大阪湾の美しさに思わず2人は見とれていた。間もなくジェット機は、太平洋上空に出て一定の高度に達し水平飛行に移った。機内の「シートベルトをお締め下さい」のサインも消え、乗客たちは機内を自由に歩き回れるようになった。
やがて機内でのドリンク・サービスと夕食の後、満腹感と連日の疲れが出たためか、機内で上映された映画も見ずに、ぐっすりと眠ってしまった。一体、何時間くらい眠ってしまったのだろう。ふと気が付くと朝食のサービスが始まっていた。
「おやっ?先刻、食べたばかりじゃないか」
「そうね」と幸子が答える。
「まもなく当機は、サンフランシスコ国際空港に着陸致します。座席を元の位置にお戻しになり、シートベルトをしっかりとお締め下さい」
という機内放送が流れ、次第に高度を下げていくジェット機の窓を通してみると、薄い雲の空の下に真白なサンフランシスコ湾に架かる「金門橋」(Golden Gate Bridge)が玩具の橋の様に見えてきた。1958年8月「ネバダ丸」で太平洋を旅し、9日目の朝、サンフランシスコ湾に到着し、船のブリッジから朝日を受けて、金色に輝いていた「金門橋」を目にした時、「ついにアメリカに来たのだ」というあの時の感激が、再びわたしの脳裏に甦った。段々と高度を下げていく飛行機の窓を通して、その先に真白な建物が立ち並ぶ市街地が眼下に広がる。
「見てごらん、サンフランシスコの街があんなに綺麗に見えるよ」
「あらー、本当。久し振りだわ」
UA810便は、無事サンフランシスコ空港に着陸。飛行機を降り、空港の長いコンコースを通って入国審査や通関も済ませたわたしたちは、再びアメリカの土地を踏むことが出来た。
「飛行機だと早いわね、眠ったと思ったら、もうサンフランシスコね。初めてアメリカに来たときは、大変だったわね」
「あれから何年になるかな?」
「22年よ」
タクシー乗り場から、サンフランシスコ市内のユニオン・スクエアのホテルにタクシーで向かった。
「ウエヤ ユー フロム?ミスター」(Where you from Mr. ?:旦那は何処から来たの?)
「オーサカ。」
「オーサカ?ワット?大阪って、日本だろ?どうして旦那さん達は英語が話せるのかね」
と黒人のタクシー・ドライバーが聞いた。
「長くニューオーリンズに住んでいたからね。ニューオーリンズ慈善病院のドクターだった」
「マイ ロード! 驚いたよ。わたしはルイジアナ州バトン・ルージュの出身だよ」と、南部訛りの英語が返ってきた。
ホテルに着くまで、そのドライバーと約20分間、ずっとわたしたちは楽しく話を続けていた。タクシー料金が21ドルだったが、黙って握手をする様にして25ドルをドライバーに手渡すと、
「エンジョイド トーキング」(楽しく話をしたよ)
「サンキュー ベリー マッチ、ドクター」
ホテルに着いた2人は、カウンターで思わぬメッセージを受け取った。それは、神戸アメリカ総領事館に勤務していたジョージ・ケフリー領事からのものである。ケフリー夫妻は、わたしがアメリカ心臓病学会でフェローに選ばれ、その授与式のためサンフランシスコに来る事を知り、わたし達をその日のディナーに招待してくれたのである。夕方、ホテルヘ車で迎えに来てくれたケフリー領事は、満面の笑みを浮かべて、
「ようこそ、いらっしゃいましたサンフランシスコへ。タカシナ・センセイ」
と流暢な日本語で挨拶し、わたしたちをドライブに誘い、しばらくサンフランシスコ市内を案内した後、空から見た「金門橋」の橋の上を、今度はケフリー領事の車でドライブすることになった。この橋は「ネバダ丸」でアメリカに到着し、初めてアメリカ西海岸の玄関口だったのだ。
「まあ、懐かしいわ。この橋の下を22年前に通ったのよ」
ケフリー領事は、わたしたちが1958年に船でアメリカに来た事を前から知っていた。その細やかな気配りに、わたし達は言い知れぬ温かさを感じた。やがてケフリー領事は金門橋を越えた所にあるレストランの前の駐車場に車を停めた。夕暮れになってレストランの窓を通して見える赤や黄、ブルーの宝石が煌くようなイルミネーションに輝く、サンフランシスコの夜景の素晴らしさは喩えようがない美しさだ。
「この度は、アメリカ心臓病学会のフェローになられて、オメデトウございます。タカシナ・センセイ」
心の篭ったケフリー領事夫妻のもてなしに、わたし達は本当に心を癒された思いであった。
その翌日からサンフランシスコ・コンベンション・センターで始まった学会には、アメリカばかりでなく世界中から心臓病専門医が集まり、その数は2万人を超える大国際会議となった。学会3日目の夕方、わたしたちは市内の授与式会場へと向った。広い控室で新しくフェローに選ばれたドクターたちは、それぞれ真っ赤なビロード地に、2本の紺色の太い線の入ったガウンに着かえた後、ロビーで待っていた。その時である。
「ケイ!おめでとう!」
と声を掛けてくれたのは、満面に笑顔を浮かべたドクター・ジェームスであった。本当に久しぶりの再会であった。
「ドクター・ジェームス、ソー ナイス トゥ シー ユー」
「元気かい?フェローになって良かったね」
「ありがとう」
ところが、ドクター・ジェームスと話している時、足早に近づき
「アー ユー ドクター・タカハシ??」
と聞いてきたドクターがいた。
「いいえ、わたしはドクター・タカシナですが」
「失礼、貴方が、若手研究者特別賞を受賞された方だ、と思っていました」
そのドクターはすぐにロビーを後にして出て行った。わたしの名前が「タカシナ」なので、間違えたのだろうという事はすぐに分かった。
「幸子は一緒かい?」とドクター・ジェームスが聞いた。
「ええ、一緒ですよ」
「宜しく伝えてくれ」と、言って彼は先に会場へ向かった。
やがて、我々は先導の牧師に従って式場へと足を進めた。ホールの両脇にはフェローの両親や、夫人や家族、そして恋人や友人たちの席が設けられ、二列になって式場に一歩ずつゆっくりと入ってくる今日の主役たちに祝福の拍手を送る。
やがて賛美歌の静かな調べが、式場に流れ厳粛な授与式が始まった。牧師が「今日の素晴らしい日に、アメリカ心臓病学会の新しいフェローが誕生した事を神に感謝する」と祈りの言葉を述べ、賛美歌「わが主よ」の大合唱が式場に溢れた。引き続き、1980年度の会長であるブランデンバーグ先生が、この年次学術総会が、関係各位の協力によって成功したことを報告し、新しいフェローに対して慶びの言葉を述べた後、授与式の記念講演のスピーカーである「ダニー・ケイ」(Danny Kaye=往年のハリウッドを代表するコメディアン)を紹介した。
2.ダニー・ケイ登場
 シーンと静まり返った式場の演壇の下から、ダニー・ケイが会場の後ろから姿を現した。静かな、そして爽やかな拍手が、一斉に式場の両脇を埋め尽くした出席者の間から起こり、次第に会場全体に広がる大きな拍手となった。ダニー・ケイは慎重な面持ちで、それに応えるかのように、微笑みながらダニー・ケイは歩いていく。そして演壇の踏み段に足を掛けた。その途端、彼は踏み段に蹴躓いてしまったのだ。大袈裟に体を動かし困ったような表情で、一歩一歩(といっても、数は3段しかないのだが)踏み段を登っていく彼のコミカルな姿に式場はどっと湧いた。ワンマンショーの開幕である。濃いグリーン地に2本の黒い線の入ったガウンを身に纏ったダニー・ケイが演壇に立つと、式場を埋め尽くした参加者から、再び大きな拍手が湧き起こった。
シーンと静まり返った式場の演壇の下から、ダニー・ケイが会場の後ろから姿を現した。静かな、そして爽やかな拍手が、一斉に式場の両脇を埋め尽くした出席者の間から起こり、次第に会場全体に広がる大きな拍手となった。ダニー・ケイは慎重な面持ちで、それに応えるかのように、微笑みながらダニー・ケイは歩いていく。そして演壇の踏み段に足を掛けた。その途端、彼は踏み段に蹴躓いてしまったのだ。大袈裟に体を動かし困ったような表情で、一歩一歩(といっても、数は3段しかないのだが)踏み段を登っていく彼のコミカルな姿に式場はどっと湧いた。ワンマンショーの開幕である。濃いグリーン地に2本の黒い線の入ったガウンを身に纏ったダニー・ケイが演壇に立つと、式場を埋め尽くした参加者から、再び大きな拍手が湧き起こった。
「きょうは、ここにお集まりの皆さんにとって、何て素晴らしい日なのでしょう。しかし、わたしにとっては実に困った日になってしまいました。と言うのは、先日の夕方、わたしが家で犬を洗っていましたら、会長のブランデングバーグ先生から電話がかかってきました」
「そしてわたしに“ダニィ、今年のアメリカ心臓病学会の「フェロー」の授与式で、記念講演をお願いしたいのだが”とおっしゃる。そこでわたしは、“先生、誰か他の方と電話番号を間違えておられませんか?”と伺ったところ、答えは“ノー”。“それで一体、わたしに何を話せとおっしゃるのですか?”とお聞きしたところ、“何でもいいから、ダニ―の思ったことを話して欲しい”と、こうなのです。“それで本当に何をしゃべってもいいのですね?”と念を押したところ、答えは“イエス”。そこで、仕方なく今日の講演をお引き受けしてしまったのです」
と、言って演壇から彼の右横に座っているブランデングバーグ先生の顔を見た。眉毛を細めて如何にも困り切ったような表情と、両肩を竦めたゼスチュアに、満場の拍手と笑いがどっと会場を揺るがす。やがて間を置いてダニィ・ケイは、一語一語区切るように、映画の中で見たコメディアンの時の、おどけて機関銃の様に早口での語り口とは全く違った雰囲気でゆっくりと話し始めた。
「皆さん方もご存知の通り、わたしはずっとユニセフの仕事をしていましたが、今から十数年前の事です。いつかタイ国のバンコックを訪れたことがありました。その時、沢山の子供達に囲まれて、笑いを振り撒いていたのですが、一人だけ、どうしても笑わない子供がいるのです。どうすれば笑ってくれるのかなーと考えていたのですが、わたしはふと思いつき、ポケットからチューインガムを取り出しました。その一つをわたしの口に、そしてもう一つをその少年の口に入れてやりました。そして暫く噛んでから、わたしはチューインガムの端を指でつまんで、口の端からピュ―と伸ばして見せました。すると、その少年もわたしがやったのと同じように、自分の口からチューインガムを引き出してわたしに見せたのです」
「その時、初めて少年は楽しそうに笑ってくれました。わたしにとってその子の笑顔は本当に宝石の輝きの様に思えたのです。その少年とわたしの笑顔をポラロイド写真に撮ってくれた人が、記念にその写真をくれました。そして翌日、わたしはタイ国を後にしました」
式場は静まり返り、ダニィ・ケイの言葉に耳を傾けている。
一息おいて、彼は
「それから10年経ったある日、わたしはもう一度、別の映画の仕事でバンコクを訪れる機会に恵まれました。10年前に少年と一緒に撮った写真を、タイ国の友人達に見せて“あの時の少年にもう一度是非会いたいから探してくれないか?”と頼みました。しかし、2日経っても3日経ってもわたしには何の連絡もありません。もう10年も経っているのだから、少年も何処かに行ってしまったかも知れないと、半ば諦めかけていたのです。4日目の朝、わたしは出発準備をして、ロビーの椅子に座って友人の車を待っていました」
「その時です。一人の青年が、つかつかとわたしのところに歩み寄ってきました。“おじさん、僕を覚えていますか?”しかし、残念ながらわたしには記憶がありません。“いいえ、残念だけれど君のようなハンサムな青年には一度も会ったことがないよ”と答えました。だって今までに彼に会ったことが無かったのですから。ところがその青年はわたしの前から立ち去ろうとしません。わたしには迎えの車が来る時間です。“済まないけど、わたしはもう発たなくてはならないのでね”と言いかけた時です。その青年はポケットから二つのチューインガムを取り出しました。呆気にとられて青年の顔を見詰めているわたしに一つのチューインガムを呉れました。そしてもう一つのチューインガムを自分の口に入れました。
“まさか?!” やがてその青年はチューインガムの端を自分の口から指で摘みだし、ピュ―と伸ばしてみせました。顔中を笑いに変えて。その顔は紛れもなく10年前の少年の顔だったのです」
「わたしの肩に手を掛けて、人懐っこく微笑んでいる青年を見上げた時、まるで空を覆っていた真っ黒な雲が切れ、明るい太陽の光が空一面に広がっていくように感じ、思わず立ち上がってその青年の体を両腕でしっかりと抱きしめました」
「わたしは、一人のコメディアンです。しかし、皆様はドクターであり、『人々の心臓』の病気を治すという素晴らしいお仕事をしていらっしゃる。確かにわたしは皆様と比べると、少しは年もとっていますし、少しはお馬鹿さんで学問もありません。しかし、わたしがユニセフの仕事を通して学んだことは、わたしの笑いと愛情を持って、世界中の子供達に接することができたと言うことです」
「どうか、今日、フェロー(fellow)になられたドクターの方々が、これからも本当に人の心に触れるような立派なドクターになって下さる事をお祈りして、わたしの『愛と笑いと人生』“Love, Laugh and Life”という話を終わります。皆様方のご幸運をお祈りします」
と言って講演を終わった。彼が演壇を離れようとした瞬間、式場の全員が総立ちとなり「ウォー」という歓声と共に万雷の拍手が会場を揺るがした。ダニー・ケイは右肘を演壇につき、拳を顎に当てたまま動かない。そして、彼の両眼から涙がキラリと光って頬を濡らした。
暫くしてダニー・ケイは思い出したように後ろを振り返り、壇上にいる(先程、わたしと間違えられた)若手研究者特別賞を授与された日本人の「ドクター・タカハシ」を自分の席のところに来るように手を振ってまねいた。一体、何が始まろうとしているのか、会場の参加者にはわかろう筈がない。すると彼は
「ドクター・タカハシ、あなたは“ショジョウジ ノ ニワ”って童謡はご存知ですか?」
「はい、知っています」
「では貴方と一緒に歌いましょう」
と言って、ダニー・ケイはドクター・タカハシと共に大きな声で、
“証 証 証城寺 証城寺の庭は ツ ツ 月夜だ みんな出て 来い 来い 来い おいらの ともだち ぽんぽこ ぽんの ぽん”
と、見事な日本語で歌い出したのである。日本語の意味が分らなくても、満場のアメリカ人の参加者らは大喝采の拍手。二人で『証城寺の狸囃子』を歌い終わったダニー・ケイは、丁寧にドクター・タカハシに最敬礼をして彼のショーを終わった。
やがて、ブランデンバーグ会長に促されるようにして、演壇から今度は注意深く、一歩ずつ踏み段を降りていったダニー・ケイは、会場を埋め尽くした人々の顔を一人一人見詰めるような眼差しで、口笛を吹き鳴らし、口許に笑みを浮かべながら最後には急ぎ足で緑のガウンを翻し、会場の中央通路を通って式場を後にした。
1988年夏、ダニー・ケイは帰らぬ人となったが、彼が残してくれた世界への人々への「心の贈り物」を、わたしFACCを授与された思い出と共に、その時の感激を決して忘れる事はない。
ホテルに帰ったわたし達は、その日の緊張と興奮で一杯だった。フェローシップ授与式のために、朝からばたばたと忙しく過ごし、式場で記念写真を撮影したりした。長かった一日を振り返り、感慨無量であった。
「フェローになって本当に良かったわ。おめでとう」
「有難う、幸子。日本でやってきた医学教育に対するわたしの活動を、アメリカ心臓病学会が認めてくれたのだ」
1958年以来、共にニューオーリンズで4年間を過ごし、そして日本に帰ってから今日まで二人の男の子を育て、わたしを助けて頑張ってきているうちに、何時の間にか22年が経っていたのだ。その夜、ホテルのダイニングルームで祝ったディナーの味は格別だった。わたしたちは、窓を通して見える美しいサンフランシスコの街をいつまでも眺めていた。
帰国してから、わたしはアメリカ心臓病学会のフェローになった事を当時、大阪府医師会の副会長を務めていた兄の経昭に報告した。このことは、直ちに大阪府医師会の理事会に報告された。
わたしがフェローになった事は、1969年にクリニックを開設以来、今日まで毎月、臨床心臓病学の勉強をしてきた東淀川区の木戸友三郎先生や、淀川区の平岡健次郎先生ら、数人の友人たちに知らされた。そして急遽、今まで共に勉強してきた数人の仲間が集まり、ホテル・プラザでわたしのために祝宴を催してくれたことは何よりも嬉しく、仲間と共に美酒に酔った一時であった。
それから2年後の1982年、わたしは大阪府医師会より長年に亘る地区医師会員に対する臨床心臓病学の教育活動が認められ学術最優秀賞を授与された。
【・・・次回に続く】
※「わたしのパスかる」へのご感想をぜひお寄せください。 office@jeccs.org