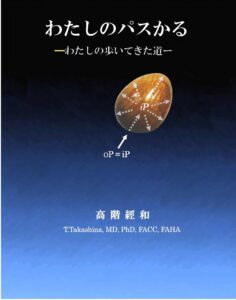ジェックスの設立者で理事長の髙階經和先生が、お生まれになった1929年から現在進行中の研究成果まで、90年を超える人生と研究をみずからまとめておられます。
内容はもちろん、読み物としても大変興味深い「自叙伝」となっています。ぜひお楽しみください!
*****************************************************
『わたしのパスかる!』(連載第16回)
ーわたしの歩いてきた道ー
ジェックス理事長 髙階 經和
第4章:-1995年~2022年-
1.阪神淡路大震災が阪神大空襲を思い出させた
1995年1月17日、私にとって忘れることのできない瞬間であった。それはつい昨日のことのようでもあり、同時に遠い昔見た映画の一場面のようでもある。しかし、現実の記憶としてわたしの残りの半生から決して消えることはないだろう。
午前5時35分、いつものように起床し洋服に着替えて洗面所に入り顔を洗った後、これから髭を剃ろうとした時である。「ゴー」という物凄い地鳴りがした途端にわたしの体が「ガン」と足下から突き上げられたように感じ、体が一瞬浮き上がったようになった。わたしはとっさに何かの大爆発が起こったと思った。それに続いて家全体が上下左右に大きく揺れ始めた。家全体が「バリバリ」と音をたて巨大な目に見えぬ恐ろしい自然の力で揺り動かされ、わたしは洗面所から飛ばされないように、必死になって両手で窓枠と洗面台を握りしめていた。
まるで暴風の海の真っ只中に、突然小舟で投げ出されたような物凄い揺れであった。幸子はその時台所にいてガスを付けたばかりであったが、横揺れが始まった途端ガスの炎が左右に大きく揺れたのが目に入り、とっさに床に横たわりながらも火を消すのが精一杯だった。必死になって体が横揺れで飛ばされないようにするのがやっとのことだった。
そして恐怖の15秒が過ぎた。辺りは真っ暗な闇。電気、水道、ガス、そして電話などのライフラインの全てが一瞬のうちに止まってしまった。わたしも最初、声を出すことさえできなかったが、暫くして「大丈夫か!」とようやく声を掛けることが出来た。「大丈夫よ」と暗闇の中から返事が返ってきた。お互いに無事であることを確認してから、真っ暗な家の中をそろそろと這うように歩き、書斎のドアを開けたが、途端に足下に何かがあることに気付いた。重いディクタフォンが部屋の端からドアのところまで飛んできていた。
やっとのことで机の引き出しを手探りで開け、懐中電灯を取り出した。その明かりを頼りに部屋の中を見渡してみたが、暫くは一体何処になにがあるのか、何が壊れたのか考える余裕など全くなかった。「とにかく屋外に出なければ危険だ」と思ったが、玄関の靴箱が倒れ出口を塞いでいる。必死になって重い靴箱をやっとのことで起こしたが、見事に潰れている。そしてドアチェーンを外してドアを開けた時、初めからドアは外に開けることが出来たのだということに気付いた。その時は、完全に思考力を失っていたのである。
まだ外は薄暗く寒い。向かいの家も隣の家にも人がいる。そしてわたしの目には門の鉄扉が道路の方に大きく開きっぱなしになっている有様が飛び込んできた。それは道路側のブロック塀に亀裂が走り、飾りの鉄柵が真ん中で折れて、塀が大きく道路の方に倒れかかっていた。それよりも驚いたことは、道路を隔てた右側の家の塀が道路側に倒れ、家屋が全壊しているではないか!
それと同時に物凄い「シュー」という連続音と、ガス特有の異臭が鼻を突いた。とっさに「ガス漏れだ!」とわたしは叫んでいた。だが、その時わたしは不思議にも恐怖を感じていない。むしろ自分の家が潰されているのではないかという不安が真っ先に頭をよぎった。開きっぱなしになっている門を出て驚いたのは、道路が波打ち、下水のマンホールが地面より20センチぐらい高くなり、その上に大きく裂けたアスファルトが50センチ程道路の幅一杯に重なり合っていた。何ということだろう!その波打った道路を歩きながら、家の損傷の具合はどうかと見てまわった。どうやら一見したところ、家自体は傾いたり亀裂が入ったりしていないことがわかった。辺りがようやく明るくなった時、遠くからヘリコプターのブルブルという爆音が響いてきた。腕時計を見ると午前6時15分。
その時わたしは、何よりもガス漏れの場所が何処かを突き止めることが先だと思った。家の角を曲がって43号線の方へ歩いていくと、だんだん「シュー」という音が大きくなってきた。二筋目の角まで来て、初めてその通りの中央部分にあるガス管が裂けてガスが吹き出しているが、どうすることもできない。
「きっと誰かがガス漏れを知らせていることだろう」と頭の中では考えていた。その時ガス漏れを起こしている場所を中心にして四方の各辻にある電信柱の間にビニールテープが張られ、その上に「火気厳禁」と有り合わせの紙に書かれた文字が目に付いた。なんと冷静で素早い行動だろう。
道を歩いている人が口々に「ここはまだいいほうだ。43号線がえらいことになっている」と話している。わたしは急いで43号線を見た。そして目を疑った。紛れもなく43号線の上に架かっていたはずの阪神高速線の架橋が山側に崩れ落ち、その架橋を支えていた筈の鉄筋コンクリートの柱が根本から折れ曲がっているのだ。思わず背筋が寒くなる。
足早に家に帰り、家内にそのことを告げた。しかし、まだその時点では、その後のラジオのニュースが刻々と知らせる淡路島北淡町を震源地としてマグニチュ−ド7.2の地震のため、神戸市を初め阪神間の各都市が大被害を被ったという事実を知らせていたが、実感は沸いてこなかった。
家から電話を掛けようとしたが、何処にも通じない。やっとのことで近くにある公衆電話からクリニック婦長の後内さんのところに電話がつながり、「我々は大丈夫です。今日はクリニックには行けないので宜しく」との連絡がとれたのが、午前7時20分であった。
やがて飛来したヘリコプターの絶え間ない爆音、救急車のサイレン、絶えず体に感じる震度3の余震の繰り返しで、半日は呆然としている内に過ぎていった。そして午後1時30分に家の電話が鳴ったが、その時ガス漏れの音と異臭が消えているのに気付いた。
「もしもし、お父様!大丈夫?經啓です。」と電話の向こうで叫んでいる。
「えらいことになった。塀が倒れかけている。我々は無事だ」
「そんなの軽い、軽い、よかった!」
と次男が思わず涙声で話している。東京では刻々と伝わるテレビのニュースに長男・次男夫婦は最悪の事態を想定していたという。特に次男はわたしがその前日の朝、次男夫婦の間に生まれたばかりの長女を見に行ったばかりだったので、その前日にわたしが別れに来たのだと思ったのに違いない。本当にやりきれない気持ちだったことだろう。
数日前から風邪のため幸子は39度の高熱が続き、その日も余震が続く中ほとんど一日中布団の中で過ごしていた。かろうじて何かを口にして、ようやく気が付いた時、辺りはすでに暗くなっていた。西の空は真っ赤に燃えてちょうど50年前の阪神大空襲の時と全く同じである。「なんという光景なのだろう。わたしは一生に二度もこの光景を見ている」ふとその時の悪夢が脳裏に蘇った。
1月18日正午過ぎ、風邪の具合も少し良くなった幸子と共に、国道43号線から芦屋川の左岸を歩き、全国から救援に集まった機動隊や警察の車の間を縫いながら、国道2号線を沿ってわたし達が目にしたものは、正に筆舌に尽くしがたい。まるで映画のセットに出てくるシーンのように全壊した家々やマンション、そして押しつぶされた高層ビルの数々の惨状である。
こうして6,460名以上の方々が尊い命を亡くしてしまったのに、わたしたちは生きている。幸せだ。きっと神様が我々を救ってくださったのに違いない。身のまわりのものがあれば我々は何もいらない。これからは生まれ変わったつもりで医療を通じ人々のために尽くしていこう、とわたしは秘かに心に誓った。
そして昨日からの出来事を振り返りながら、わたしは人生の価値観をすっかり変えてしまった15秒間の現実を反芻している自分の中で、新しいエネルギーが沸いてくるのを感じていた。
さらに、阪神淡路大震災の直後、「オウム真理教」の事件が起こった。この事件は、我々がいままでに経験したことのない、弱者を引きずり込む強引な宗教集団の存在を伝え、暴走したカルト集団の恐ろしさが、人々を精神的ショックのどん底に陥れた。この全く予期していなかったふたつの事件が、当時、わが国における最大の関心事となったことは言うまでもない。
こうした予期せぬ大震災とオウム真理教のニュースのために、わたし達が長年掛かって創りあげた「イチロー君」のニュースはフッ飛んでしまった。
2.華の道へ旅立った母
1996年1月4日、母「浜尾」は地震直後の5月に左口腔内肉腫のため大阪逓信病院耳鼻科で手術を受けたが、見舞いに行くたびに「あんなに怖い思いをしたことがない」と8階の兄の大黒橋ビルが大揺れに揺れたときの地震の恐ろしさを話していたが、それがきっかけとなり口腔内肉腫が発生したのに違いない。9月には一応、大阪逓信病院から退院したが病院での生活が本当に嫌だったのだろう。「もう二度と病院には戻りたくない」と繰り返し話していた。
姉の好子や、兄の經昭、家内の幸子などが殆ど交代で母の家に泊まり、わたしも週に一度は泊まって母の左頬に出来てしまった潰瘍孔のガーゼ交換や、下着の交換、そしてトイレ、時間ごとに鎮痛剤坐薬を入れるなど、身をもって「在宅終末期医療」の難しさを体験した。それでもわたしは翌日の診察には、明るく患者さんに接し、一言も母のことについて話さなかった。
段々に体力の低下していく自分の身に死期の近いことを悟った母が亡くなる2日前に「本当に貴方達には世話になった。有り難う。」と繰り返し礼を言った言葉が今でも耳に残っている。
父が脳溢血で倒れてから、戦争中のあの厳しい時代を生き抜き、半身不随になった父を助けて診療の片腕となって働き、戦争中、焼夷弾の炸裂で全身に大火傷を負った人々のために、自分の浴衣を全て切り包帯として使っていた母、食糧難で殆ど収入のない毎日の生活の中でも、明るく振舞い、わたし達に心配させないように懸命に働いていた母の姿が今も目に浮かぶ。今日までわたし達を育ててくれた『母』は偉大な母であり、そして『華道』に励んだ『女の一生』であったとわたしは信じている。
わたしが前日に泊まり、母の看病をして家に帰った直後に、兄から電話があり、「下顎呼吸がはじまった」との知らせを聞いて、急いで大阪の母の元へとって返したが、既に母は父のいる天国へ旅立ち帰らぬ人となっていた。そして母は94歳の生涯を閉じた。
苦しみから解き放たれ、安らかな表情の母の顔を見てわたしは泣いた。男泣きに泣いた。子供の頃からわたし達四人の子供達を立派に育ててくれた母、そして小原流の家元となり一生懸命に弟子の方々の面倒を見ていた偉大な母、その母も今は父の元へ旅立った事だろう。「どうかお父様と一緒に天国からわたし達や、家族を見守って下さい。さようなら、お母様」。そして、母のため別れの句を詠んだ。
『初春に 華の道へと 旅立ちぬ 母を包みし 白き菊の香』
【・・・次回に続く】
※「わたしのパスかる」へのご感想をぜひお寄せください。 office@jeccs.org